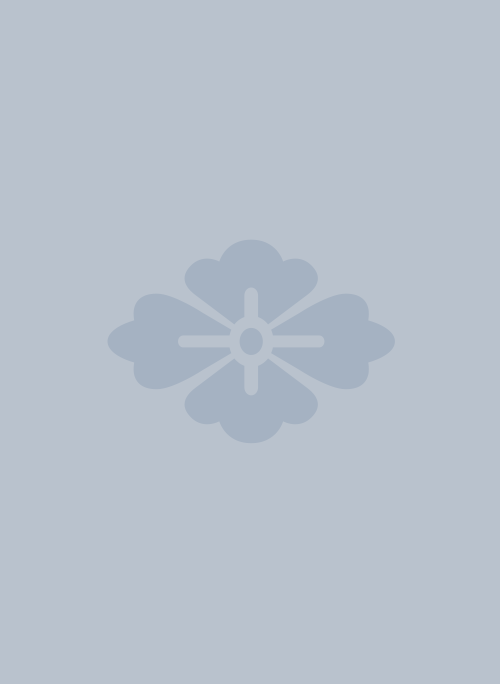屈託なく笑う三郎太に、藍もにこにこと返す。
三郎太の言い方は、さらりとして嫌みがない。
妙ないやらしさもないのは、人柄だろう。
「でも、あなたにとっては、お蓉さんのほうが、断然綺麗でしょ」
話の流れに沿って、さらりと言った藍に、三郎太が笑顔のまま固まり、一瞬後には、顔から火が出そうな勢いで、みるみる真っ赤になった。
「ななな・・・・・・何を・・・・・・。そ、そりゃ・・・・・・」
もごもごと下を向いて口ごもる三郎太を見つつ、藍はちら、とお蓉に視線をやった。
お蓉も赤くなっているが、じっと三郎太を見つめている。
「菊助。この機会に、はっきりと教えてちょうだい。彩さんの言うように、あなたはわたくしのことを、一番に想ってくれているのかしら」
「おお、お嬢さん・・・・・・」
しっかりと三郎太を見据えて言うお蓉に、三郎太は、たじたじとなる。
藍は間で、面白いものを見る子供のように、二人を交互に見た。
「この前、わたくしに可愛い下駄をくれたわね。あれは、何故なの?」
「あ、あれは・・・・・・。お嬢さんに、似合うだろうと思って・・・・・・」
「答えになってないわ。ただの気まぐれ? 主家の娘に対する、お義理なの?」
三郎太の言い方は、さらりとして嫌みがない。
妙ないやらしさもないのは、人柄だろう。
「でも、あなたにとっては、お蓉さんのほうが、断然綺麗でしょ」
話の流れに沿って、さらりと言った藍に、三郎太が笑顔のまま固まり、一瞬後には、顔から火が出そうな勢いで、みるみる真っ赤になった。
「ななな・・・・・・何を・・・・・・。そ、そりゃ・・・・・・」
もごもごと下を向いて口ごもる三郎太を見つつ、藍はちら、とお蓉に視線をやった。
お蓉も赤くなっているが、じっと三郎太を見つめている。
「菊助。この機会に、はっきりと教えてちょうだい。彩さんの言うように、あなたはわたくしのことを、一番に想ってくれているのかしら」
「おお、お嬢さん・・・・・・」
しっかりと三郎太を見据えて言うお蓉に、三郎太は、たじたじとなる。
藍は間で、面白いものを見る子供のように、二人を交互に見た。
「この前、わたくしに可愛い下駄をくれたわね。あれは、何故なの?」
「あ、あれは・・・・・・。お嬢さんに、似合うだろうと思って・・・・・・」
「答えになってないわ。ただの気まぐれ? 主家の娘に対する、お義理なの?」