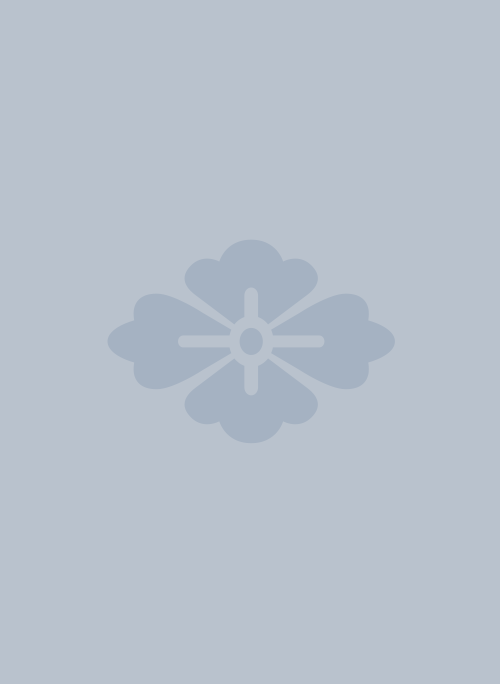与一が起き上がると、藍は早速サラシを解き、傷の状態を確かめた。
「ん。ちょっとだけ血が出てるけど、開いてはいないし、大丈夫ね」
藍は懐から出した小さな容器の蓋を開け、傷に振りかけた。
「藍さん。消毒液、持ってるんじゃないですか」
本物の消毒液を持っているくせに、何故舐めろとか言うのだ。
が、藍は再びサラシを巻き付けながら、与一に向かってべぇっと舌を出す。
「これは、よいっちゃんの分だもん。あたしの傷なんて、舐めときゃ治るもの」
「それはそれは、ありがとうございます。でも、人に舐めさすのはやめたほうがいいですね」
「だって、ほっぺたなんて、自分じゃ舐められないじゃない」
当たり前のように言う藍に、与一も思わず、なるほどね、と納得してしまう。
納得したところで、舐めないが。
「手に接吻されただけで、泣くほど怒るくせに、頬を舐められるのはいいわけですか」
呆れながら言う与一に、藍はどかっと身体をぶつけた。
足を上に乗った藍に拘束されている上、傷で腹筋があまりきかないため、与一は布団に、仰向けに寝ころんでしまう。
「ん。ちょっとだけ血が出てるけど、開いてはいないし、大丈夫ね」
藍は懐から出した小さな容器の蓋を開け、傷に振りかけた。
「藍さん。消毒液、持ってるんじゃないですか」
本物の消毒液を持っているくせに、何故舐めろとか言うのだ。
が、藍は再びサラシを巻き付けながら、与一に向かってべぇっと舌を出す。
「これは、よいっちゃんの分だもん。あたしの傷なんて、舐めときゃ治るもの」
「それはそれは、ありがとうございます。でも、人に舐めさすのはやめたほうがいいですね」
「だって、ほっぺたなんて、自分じゃ舐められないじゃない」
当たり前のように言う藍に、与一も思わず、なるほどね、と納得してしまう。
納得したところで、舐めないが。
「手に接吻されただけで、泣くほど怒るくせに、頬を舐められるのはいいわけですか」
呆れながら言う与一に、藍はどかっと身体をぶつけた。
足を上に乗った藍に拘束されている上、傷で腹筋があまりきかないため、与一は布団に、仰向けに寝ころんでしまう。