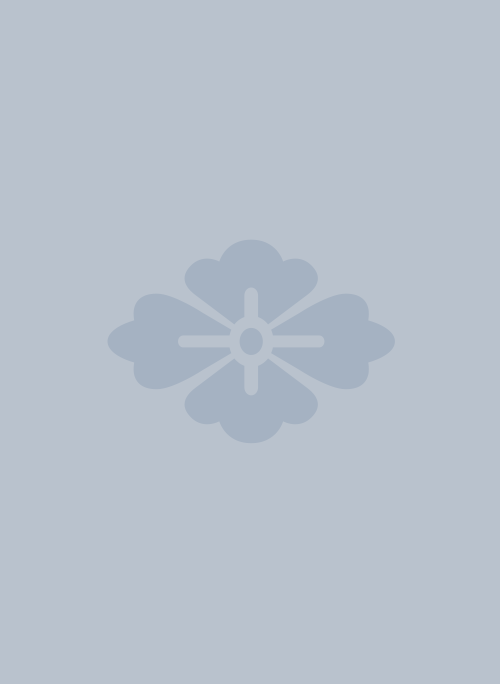「・・・・・・」
確かに、思ったよりも難しかった。
己に惚れさすということは、己の身に危険が及ぶということだ。
しかも、その危険というのは、慣れた‘命の危機’ではない。
不慣れな‘貞操の危機’なのだ。
「わかったわ。折角よいっちゃんに綺麗にしてもらったのに、また舐められるなんて、冗談じゃないわ」
「・・・・・・俺は何もしてませんが」
「あたしの手、舐めてくれたじゃない」
ひらひらと、藍が手を振る。
「舐めたわけじゃないですよ。軽く口をつけただけです。奴も、そうだったでしょう?」
藍が、思い切り顔をしかめた。
「そんなの、わかんないわよっ! 大体手に口をつけるなんて、信じられないっ!」
そうだろうか、と思いながら、与一は再びきゃんきゃんと吠える藍を見た。
「本当の接吻なら、良かったんですか?」
「ほんとの接吻?」
確かに、思ったよりも難しかった。
己に惚れさすということは、己の身に危険が及ぶということだ。
しかも、その危険というのは、慣れた‘命の危機’ではない。
不慣れな‘貞操の危機’なのだ。
「わかったわ。折角よいっちゃんに綺麗にしてもらったのに、また舐められるなんて、冗談じゃないわ」
「・・・・・・俺は何もしてませんが」
「あたしの手、舐めてくれたじゃない」
ひらひらと、藍が手を振る。
「舐めたわけじゃないですよ。軽く口をつけただけです。奴も、そうだったでしょう?」
藍が、思い切り顔をしかめた。
「そんなの、わかんないわよっ! 大体手に口をつけるなんて、信じられないっ!」
そうだろうか、と思いながら、与一は再びきゃんきゃんと吠える藍を見た。
「本当の接吻なら、良かったんですか?」
「ほんとの接吻?」