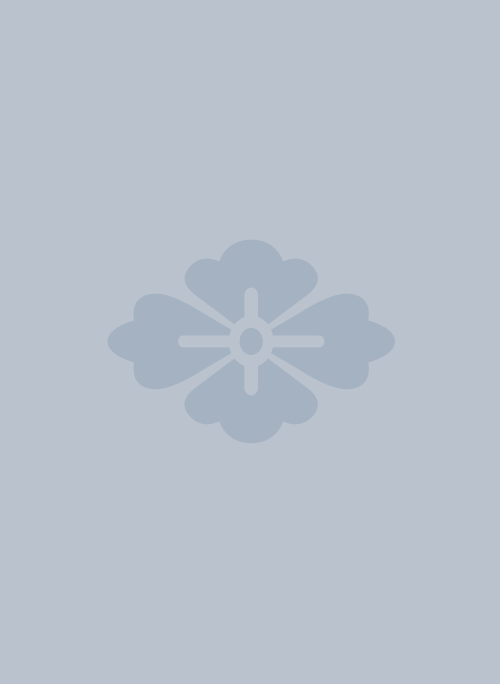「女郎なもんか。お嬢さんの話じゃ、殿様の血を引いてるようだぜ」
「お姫様ってことか?」
「まぁ、そういうことかな。直系ではないらしいけどな。本当のお姫様なら、さすがに千秋屋のお嬢さんでも、お近づきにはなれんだろうさ」
う~ん、と、与一は腕組みして考え込んだ。
下駄屋の主人・・・・・・。
どんな顔だったろう。
あまり記憶にないということは、そう印象に残るような顔でもなかったということだ。
可もなく、不可もない、平々凡々な顔の、初老の男・・・・・・。
「な、何でそんな親父と、お姫様が・・・・・・」
どうしてもわからず、腕組みしたまま唸る与一に、三郎太が気遣わしげな視線を投げる。
「・・・・・・何だ?」
「いや・・・・・・。お前、まさかとは思うが、あそこの奥方に懸想してるんじゃないだろうな?」
思わず与一は、膝先にあった湯飲みを、蹴飛ばしそうになった。
「お姫様ってことか?」
「まぁ、そういうことかな。直系ではないらしいけどな。本当のお姫様なら、さすがに千秋屋のお嬢さんでも、お近づきにはなれんだろうさ」
う~ん、と、与一は腕組みして考え込んだ。
下駄屋の主人・・・・・・。
どんな顔だったろう。
あまり記憶にないということは、そう印象に残るような顔でもなかったということだ。
可もなく、不可もない、平々凡々な顔の、初老の男・・・・・・。
「な、何でそんな親父と、お姫様が・・・・・・」
どうしてもわからず、腕組みしたまま唸る与一に、三郎太が気遣わしげな視線を投げる。
「・・・・・・何だ?」
「いや・・・・・・。お前、まさかとは思うが、あそこの奥方に懸想してるんじゃないだろうな?」
思わず与一は、膝先にあった湯飲みを、蹴飛ばしそうになった。