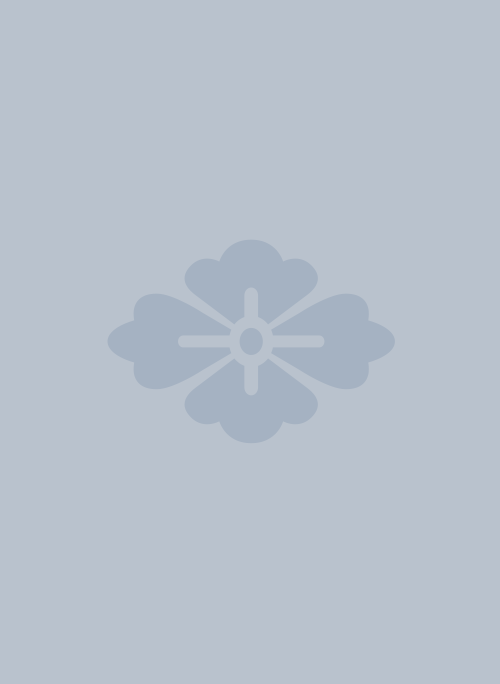「俺ができるのは、せいぜい贈り物をして、ご機嫌を取るぐらいだな」
「いや、お前とお嬢さんなんて、大したことはない」
「! そうか?」
ぱっと明るい顔になって、三郎太が身を乗り出す。
「それより、お嬢さんの友達だっていう下駄屋の奥方。そっちのほうが、やばくないか?」
噛み付くように言う与一に、三郎太は何のことだかわからないというように、きょとんとした。
「お嬢さんが十七ってことは、下駄屋の奥方もそれぐらいってことじゃないのか?」
「ああ、そのことかい」
ようやく合点がいったように、三郎太が息をつく。
そしてにやりと笑うと、元のように、与一に顔を近づけた。
「そうだな。何とあそこの奥方、うちのお嬢さんより、年下なんだぜ」
目玉が落ちんばかりに目を見開き、口をあんぐり開けた与一は、ゆっくりと視線だけを動かして、三郎太を見た。
「いや、お前とお嬢さんなんて、大したことはない」
「! そうか?」
ぱっと明るい顔になって、三郎太が身を乗り出す。
「それより、お嬢さんの友達だっていう下駄屋の奥方。そっちのほうが、やばくないか?」
噛み付くように言う与一に、三郎太は何のことだかわからないというように、きょとんとした。
「お嬢さんが十七ってことは、下駄屋の奥方もそれぐらいってことじゃないのか?」
「ああ、そのことかい」
ようやく合点がいったように、三郎太が息をつく。
そしてにやりと笑うと、元のように、与一に顔を近づけた。
「そうだな。何とあそこの奥方、うちのお嬢さんより、年下なんだぜ」
目玉が落ちんばかりに目を見開き、口をあんぐり開けた与一は、ゆっくりと視線だけを動かして、三郎太を見た。