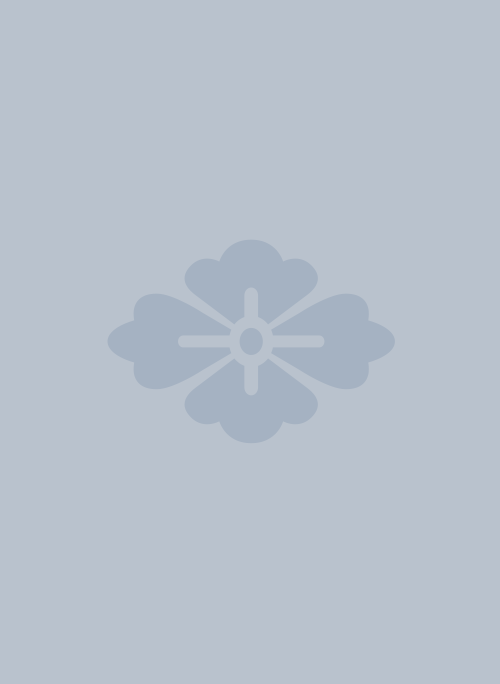「? お嬢さんも、お前を気に入ってくれてるって、自分で言ってたじゃねぇか」
何を今更、と、与一は呆れた。
「うん、まぁ、そうなんだけどな」
でへへ、と笑い、しきりに鼻の下をこすりながら、三郎太は落ち着き無く視線を彷徨わせる。
「でもよぅ。お嬢さんは、まだ十七だしな。滅多なことは、できねぇよ」
「十七?」
与一は耳を疑った。
下駄屋の奥方とここのお嬢さんは、友達だと言っていた。
ということは、下駄屋の奥方も、十七ぐらいということか。
下駄屋の主人は、どう見ても五十代、若くても四十後半だろう。
「な、驚くだろう? 俺は奉公上がりだし、すでに二十四だ。七つも下のお嬢さんに、おいそれと手出しはできん」
与一の驚きを、自分とお嬢さんの歳の差だと思った三郎太は、ため息をついて遠い目をした。
何を今更、と、与一は呆れた。
「うん、まぁ、そうなんだけどな」
でへへ、と笑い、しきりに鼻の下をこすりながら、三郎太は落ち着き無く視線を彷徨わせる。
「でもよぅ。お嬢さんは、まだ十七だしな。滅多なことは、できねぇよ」
「十七?」
与一は耳を疑った。
下駄屋の奥方とここのお嬢さんは、友達だと言っていた。
ということは、下駄屋の奥方も、十七ぐらいということか。
下駄屋の主人は、どう見ても五十代、若くても四十後半だろう。
「な、驚くだろう? 俺は奉公上がりだし、すでに二十四だ。七つも下のお嬢さんに、おいそれと手出しはできん」
与一の驚きを、自分とお嬢さんの歳の差だと思った三郎太は、ため息をついて遠い目をした。