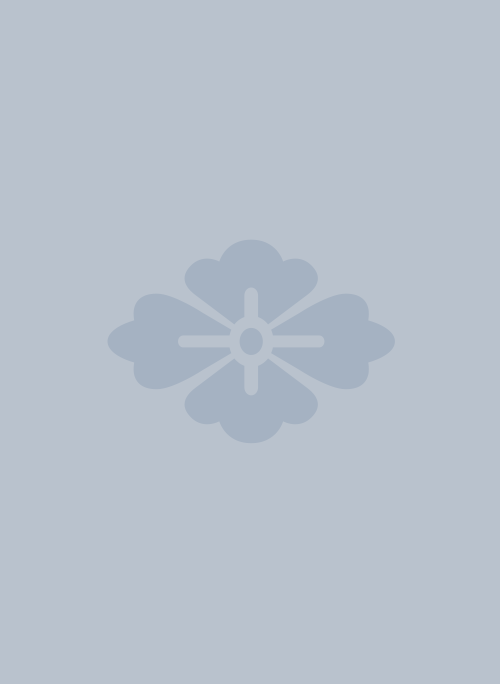少し笑って言う与一に、三郎太も笑いかけた。
「まぁな。でも面白いぜ」
自分に絶対被害がないなら、面白いのかもな、と、与一は曖昧に笑った。
「そうそう。辰巳が男色家なら、たとえ自分の想い人が下駄を作ってもらうために足を差し出しても、妙な気を起こさないしな」
確か三郎太は、お嬢さんの下駄を辰巳に作ってもらっていた。
辰巳が男色家でなかったら、目の前で自分の想い人の足をあんなに撫で回されたら、良い気はしないだろう。
「ばっか! な、何言うんだよ」
途端に真っ赤になって、三郎太は与一の肩をばしんと叩いた。
「お、想い人だなんて・・・・・・。俺ごときが、そんな大それた・・・・・・」
「まぁな。でも面白いぜ」
自分に絶対被害がないなら、面白いのかもな、と、与一は曖昧に笑った。
「そうそう。辰巳が男色家なら、たとえ自分の想い人が下駄を作ってもらうために足を差し出しても、妙な気を起こさないしな」
確か三郎太は、お嬢さんの下駄を辰巳に作ってもらっていた。
辰巳が男色家でなかったら、目の前で自分の想い人の足をあんなに撫で回されたら、良い気はしないだろう。
「ばっか! な、何言うんだよ」
途端に真っ赤になって、三郎太は与一の肩をばしんと叩いた。
「お、想い人だなんて・・・・・・。俺ごときが、そんな大それた・・・・・・」