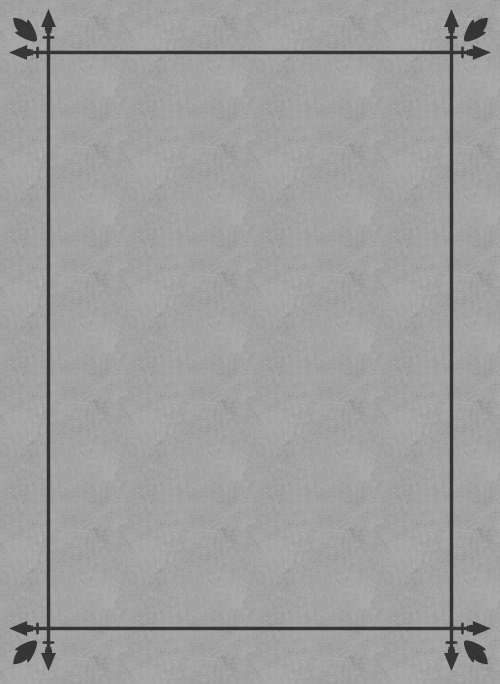ぎゅうっときついほど抱きしめられる感覚に胸が苦しくなる。
「―――会いたかった」
もう一度、ゆっくりと吐きだされた言葉に目を瞑る。
そんなの。
「…うそ」
「嘘じゃないよ。本当に会いたかった」
…嘘だ。だって、あの時あたしに……、
「電話にも出てくれないし、実家に帰ってると思ったのに帰ってないし、どこに行ったのか分からないし…」
「……」
「なぜか聖の電話に出るし、かと思えば聖の家にいるっていうし…」
「それは、」
訳を話そうとすれば、ぐっとさらに抱きしめられて拒まれる。
「僕がどんな気持ちでいたか分かる…?」
そんな。そんな勝手なこと言わないでよ。
ぐっと身じろぎして、高橋と向き合う。
間近で見上げた高橋は真っ直ぐにあたしを見つめていて。
その顔を見て、なぜか涙がこみあげてくる。
「どんな気持ちって、分かるわけないじゃん!」
「分かってよ」
「分かんないよ!だって…、だって、他の人好きになれって言った…!」
ぽん、とグーで高橋の肩を叩く。
「あたしを突き放したのは高橋じゃん!」
あたしの為みたいなことを言いながら。
突き放すようなことを言ってきたくせに、心配して。
そんな高橋が何を考えてるかなんて、あたしが分かるわけがない。
「あたしのこと考えてるみたいな言い方するけれど、全然分かってないのは高橋じゃん…」
ぽん、ぽんと叩き続けるあたしに、高橋は抵抗もせず黙って受け止める。
ぐっと唇を噛みしめる。
全然分かってない。
「傷を気にしないって高橋が言ってくれたからってそれだけで高橋と付き合ったりしないよ!!!」
そんな単純な理由で好きになったんじゃない。あの時、好きって言ったんじゃない。
「そんな理由で付き合ってると思われてたなんて…むかつく…っ!」
「―――会いたかった」
もう一度、ゆっくりと吐きだされた言葉に目を瞑る。
そんなの。
「…うそ」
「嘘じゃないよ。本当に会いたかった」
…嘘だ。だって、あの時あたしに……、
「電話にも出てくれないし、実家に帰ってると思ったのに帰ってないし、どこに行ったのか分からないし…」
「……」
「なぜか聖の電話に出るし、かと思えば聖の家にいるっていうし…」
「それは、」
訳を話そうとすれば、ぐっとさらに抱きしめられて拒まれる。
「僕がどんな気持ちでいたか分かる…?」
そんな。そんな勝手なこと言わないでよ。
ぐっと身じろぎして、高橋と向き合う。
間近で見上げた高橋は真っ直ぐにあたしを見つめていて。
その顔を見て、なぜか涙がこみあげてくる。
「どんな気持ちって、分かるわけないじゃん!」
「分かってよ」
「分かんないよ!だって…、だって、他の人好きになれって言った…!」
ぽん、とグーで高橋の肩を叩く。
「あたしを突き放したのは高橋じゃん!」
あたしの為みたいなことを言いながら。
突き放すようなことを言ってきたくせに、心配して。
そんな高橋が何を考えてるかなんて、あたしが分かるわけがない。
「あたしのこと考えてるみたいな言い方するけれど、全然分かってないのは高橋じゃん…」
ぽん、ぽんと叩き続けるあたしに、高橋は抵抗もせず黙って受け止める。
ぐっと唇を噛みしめる。
全然分かってない。
「傷を気にしないって高橋が言ってくれたからってそれだけで高橋と付き合ったりしないよ!!!」
そんな単純な理由で好きになったんじゃない。あの時、好きって言ったんじゃない。
「そんな理由で付き合ってると思われてたなんて…むかつく…っ!」