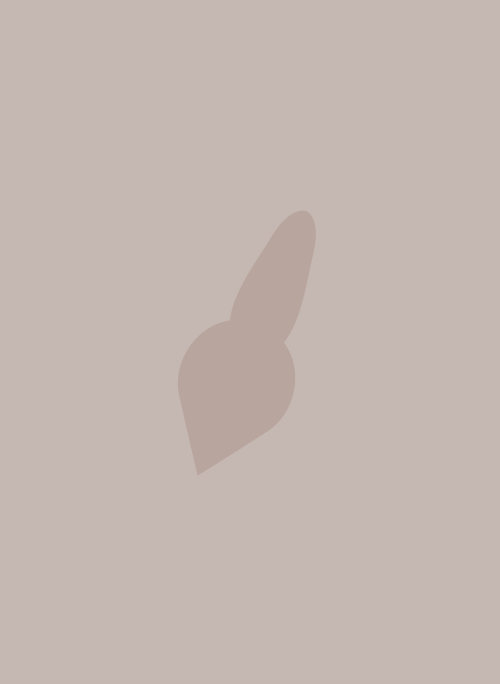未だ、心臓は早く脈打っていて、苦しい。
あたしは、布団から顔を出して新鮮な空気をゆっくりと吸った。
何度も繰り返せば心臓は落ち着いていき、今はもう平常の早さで脈打っている。
あたしはベッドに座りなおした。
すると、ドアからノックする音が聞こえた。
あたしはお兄ちゃんであってほしくないと思って、咄嗟に「お母さん?」と言った。
だけど、あたしの願いは叶わなかった。
「誰がお母さんだ。誰が」
ドアから出てきたのはお兄ちゃんだった。
何故か今日は、一段と銀色の髪が綺麗に見えた。
「どうしたの」
「どうしたのって、顔を見に来たんだよ」
不思議そうな顔を浮かべたお兄ちゃんはそう言いながらあたしの前に座った。
いつものようにお兄ちゃんはあたしの頭を撫でようとした。
あたしは思わずその手を払ってしまった。
今までそんなこてをされたことがなかったお兄ちゃんは驚いて、目を見開いていた。
謝るべきだろうが、あたしの口からは謝罪の言葉でない言葉が出た。
「お兄ちゃん、もう来なくていいよ」
あたしは、布団から顔を出して新鮮な空気をゆっくりと吸った。
何度も繰り返せば心臓は落ち着いていき、今はもう平常の早さで脈打っている。
あたしはベッドに座りなおした。
すると、ドアからノックする音が聞こえた。
あたしはお兄ちゃんであってほしくないと思って、咄嗟に「お母さん?」と言った。
だけど、あたしの願いは叶わなかった。
「誰がお母さんだ。誰が」
ドアから出てきたのはお兄ちゃんだった。
何故か今日は、一段と銀色の髪が綺麗に見えた。
「どうしたの」
「どうしたのって、顔を見に来たんだよ」
不思議そうな顔を浮かべたお兄ちゃんはそう言いながらあたしの前に座った。
いつものようにお兄ちゃんはあたしの頭を撫でようとした。
あたしは思わずその手を払ってしまった。
今までそんなこてをされたことがなかったお兄ちゃんは驚いて、目を見開いていた。
謝るべきだろうが、あたしの口からは謝罪の言葉でない言葉が出た。
「お兄ちゃん、もう来なくていいよ」
![[短編]お兄ちゃん、これからは(5/11) | 野いちご](https://www.no-ichigo.jp/assets/1.0.777/img/logo.svg)