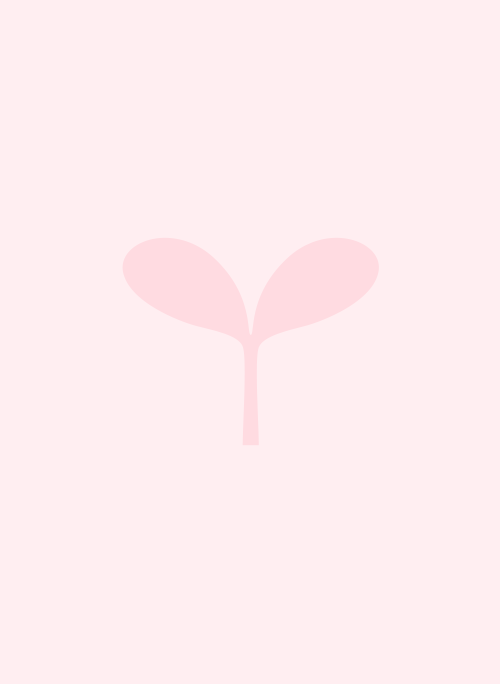小さく飛び跳ねている息子の頭を撫でてやりながら顔を上げる。
ふと少年の一人と目が合った。
きっと焼き芋をくれた子だろう。
ニコリと微笑む。
すると、少年は嬉しいような照れくさいような、ちょっと複雑な顔で俯き、棒で落ち葉を突っつきだした。
どこか達也と似ている。
逸子の頬をまた涙が伝った。
この子もすぐにあれくらいの年になって、たくさんの友達を作って、素敵な出会いを繰り返していくのだろう。
その時私は、生きているだろうか?
ふと少年の一人と目が合った。
きっと焼き芋をくれた子だろう。
ニコリと微笑む。
すると、少年は嬉しいような照れくさいような、ちょっと複雑な顔で俯き、棒で落ち葉を突っつきだした。
どこか達也と似ている。
逸子の頬をまた涙が伝った。
この子もすぐにあれくらいの年になって、たくさんの友達を作って、素敵な出会いを繰り返していくのだろう。
その時私は、生きているだろうか?