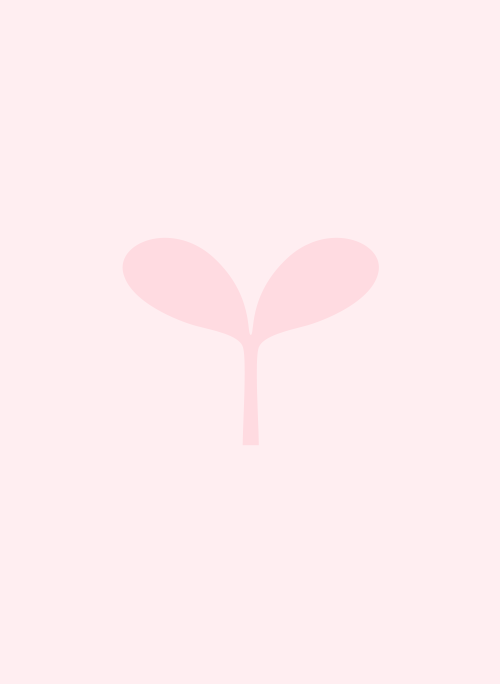赤錆びたトラス橋が流れ去っていく。
頭にサイレンを付けた町役場のトラックが小さくなっていく。
道端には無数の春紫苑が咲き誇り、まるで二人を祝福するかのように白く小さな花を揺らしていた。
帰ってくればいい。
何度でも。
達也は百合子を抱きしめ、いつまでも靖之に手を振り続けた。
ここが故郷なのだ。
たった一つのふるさとなのだ。
空は高く晴れ渡っていた。
そして三人の物語は、またここから始まっていく。
了
頭にサイレンを付けた町役場のトラックが小さくなっていく。
道端には無数の春紫苑が咲き誇り、まるで二人を祝福するかのように白く小さな花を揺らしていた。
帰ってくればいい。
何度でも。
達也は百合子を抱きしめ、いつまでも靖之に手を振り続けた。
ここが故郷なのだ。
たった一つのふるさとなのだ。
空は高く晴れ渡っていた。
そして三人の物語は、またここから始まっていく。
了