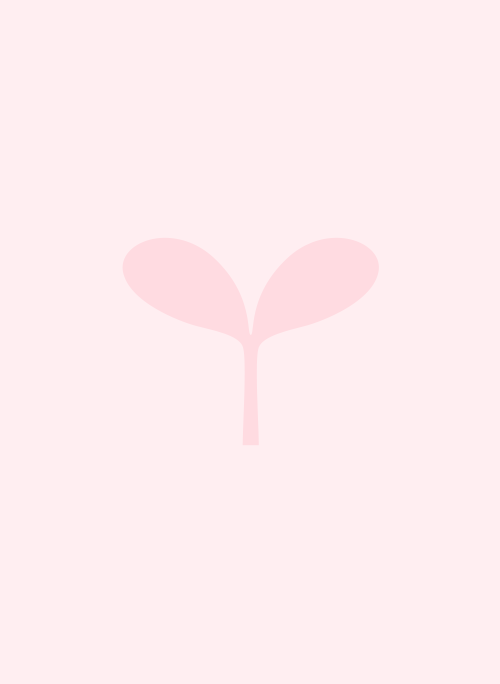「教えてくれたっていいじゃない」
「わりぃ」
「何がわりぃ、よ」
百合子が達也の口真似をして、軽く足に蹴りを入れる。
「はは……痛って!」
達也は身をよじってホームの端っこに避難し、二年前まで父親と暮らしてきた故郷の山を見つめた。
「……来ないね」
ハンドバッグを肩に掛け直し、百合子が俯きがちに呟く。
「汽車」
「ん……ああ」
達也がレールの先に視線を移すと、柔らかい風が頬をすり抜けた。
「わりぃ」
「何がわりぃ、よ」
百合子が達也の口真似をして、軽く足に蹴りを入れる。
「はは……痛って!」
達也は身をよじってホームの端っこに避難し、二年前まで父親と暮らしてきた故郷の山を見つめた。
「……来ないね」
ハンドバッグを肩に掛け直し、百合子が俯きがちに呟く。
「汽車」
「ん……ああ」
達也がレールの先に視線を移すと、柔らかい風が頬をすり抜けた。