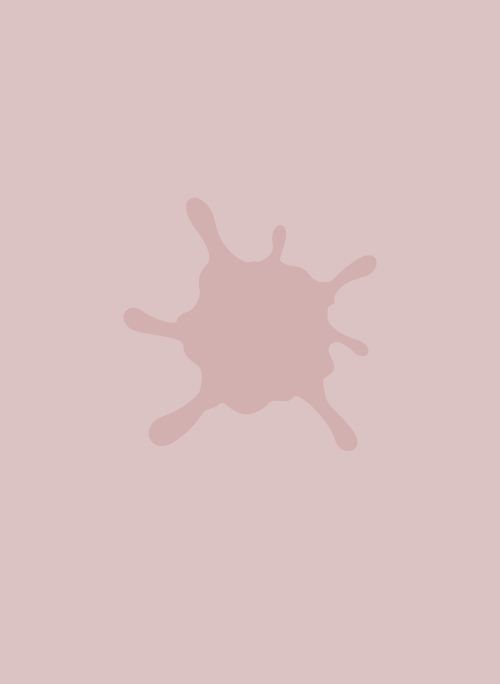「筆箱を忘れてしまったんです」
「そっか。そろそろ行かないと遅刻するかも」
「依田君」
その言葉に依田先輩が振り返る。だが、一足先にわたしは彼女を見て胸がつかまれたように痛んだ。
彼女はわたしを睨んでいたのだ。
依田先輩が振り返る前に、彼女は笑顔に戻る。
「行きますね」
わたしは教室に戻ると、自分の机の上に置きっぱなしになっていたペンケースを手に取る。
教室の外をのぞくと、依田先輩はもうどこにもいなかった。
少し胸を撫で下ろし、階段をおりていく。
あんなことは珍しいことではなかった。でも、そんなに私は見知らぬ人から敵意をぶつけられ続けるくらい邪魔な存在なんだろうか。
声に出せない想いを抱き、天を仰いだ。だが、唇を噛みしめ、階段をおりていく。
「そっか。そろそろ行かないと遅刻するかも」
「依田君」
その言葉に依田先輩が振り返る。だが、一足先にわたしは彼女を見て胸がつかまれたように痛んだ。
彼女はわたしを睨んでいたのだ。
依田先輩が振り返る前に、彼女は笑顔に戻る。
「行きますね」
わたしは教室に戻ると、自分の机の上に置きっぱなしになっていたペンケースを手に取る。
教室の外をのぞくと、依田先輩はもうどこにもいなかった。
少し胸を撫で下ろし、階段をおりていく。
あんなことは珍しいことではなかった。でも、そんなに私は見知らぬ人から敵意をぶつけられ続けるくらい邪魔な存在なんだろうか。
声に出せない想いを抱き、天を仰いだ。だが、唇を噛みしめ、階段をおりていく。