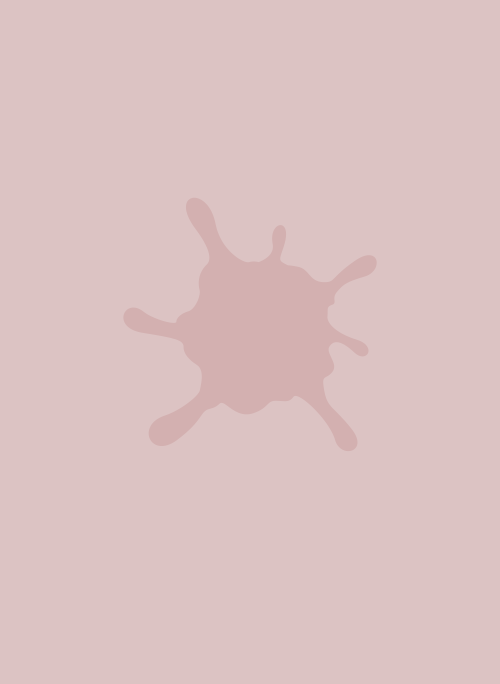彼女たちと目が合い、わたしは体をびくりと震わせた。
一人が口角をあげて微笑み、わたしの傍まで寄ってくる。
肩をすぼめ、唇を軽く噛む。
「前原さんは卓球なんだね」
彼女たちは顔を見合わせて笑う。だが、その笑いは過去の断片を蘇らせる。
わたしは無言でうなずいた。
彼女たちは西原先輩と一緒に帰った日、わたしのことをとやかく言っていた人たちだったのだ。
「可愛いって得だよね。大人しくしていれば男がかまってくれるんだもの」
二人は不服そうに品定めをするような目でわたしを見る。
「否定しないんだ。自分で自分を可愛いとでも思っているの?」
「思ってません」
「嘘。思っているんじゃないの? そんな顔してるもん」
自分の顔が好きなど殆どの人は思わないだろう。わたしも自分の顔は好きではなかった。だが、否定してもしなくても彼女たちの考えがすべてなのだ。
一人が口角をあげて微笑み、わたしの傍まで寄ってくる。
肩をすぼめ、唇を軽く噛む。
「前原さんは卓球なんだね」
彼女たちは顔を見合わせて笑う。だが、その笑いは過去の断片を蘇らせる。
わたしは無言でうなずいた。
彼女たちは西原先輩と一緒に帰った日、わたしのことをとやかく言っていた人たちだったのだ。
「可愛いって得だよね。大人しくしていれば男がかまってくれるんだもの」
二人は不服そうに品定めをするような目でわたしを見る。
「否定しないんだ。自分で自分を可愛いとでも思っているの?」
「思ってません」
「嘘。思っているんじゃないの? そんな顔してるもん」
自分の顔が好きなど殆どの人は思わないだろう。わたしも自分の顔は好きではなかった。だが、否定してもしなくても彼女たちの考えがすべてなのだ。