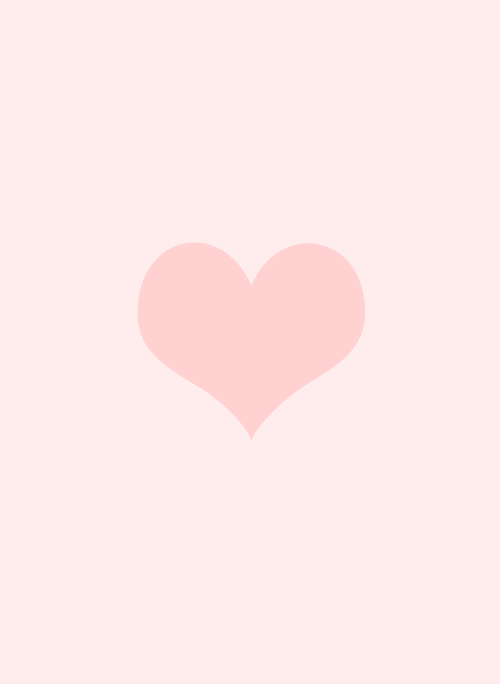足音を立てないよう気をつけて近づいていくと、彼は大地の上に寝転がっていた。
地に広がる赤が私の目を奪う。
もう、それしか見ることができなくなる。
声をかけられず遠巻きに見ていると、彼は懐から笛を取り出してじっとそれを見つめていた。
悩ましげな表情が、草木に滲んでいく。
話すことなく帰ろうとしたとき、迂闊にも私の足が枯れ枝を踏んでしまった。
「あ」
弾みで声が出たときには後の祭りで。
うっかり合ってしまった視線に、それ以上弁解の余地は無かった。
睨むように鋭い双眸で見つめられ、
「ご、ごめんなさい…」
ぽつりと謝ってうつむいたまま身動きが取れなかった。
逃げても口を開いても、怒られるのは目に見えていた。
けれどそんな私の予想とは反対に、彼は怒ることはしなかった。
「撫子」
今まで聞いたどの声より自信が無い声で私の名をつぶやき、
「…ごめんな」
今まで聞いたどの声より優しくて悲しくてあたたかい響きを放った。