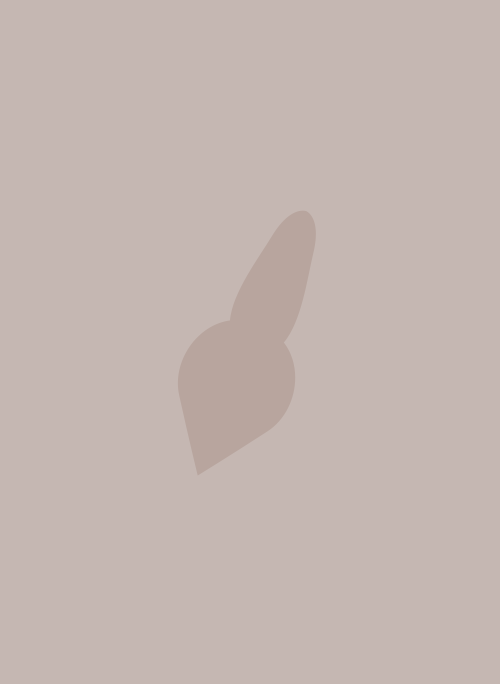余りの切ない姿に手を差し伸ばそうとするが、じぃに届くまでにその手は遮られた。
「そろそろ別れの時間だ」
そのまま腰に腕を回され俵担ぎにされ体が宙に浮く。
「舌を噛まないように気を付けろよ」
そう言って駆け出した重祢の言葉を人質として守って舌を奥へと引っ込める。
まるで走馬灯のように御輿やじぃ達が居る場所が段々と遠くなっていく。
規則的な振動が脳髄に響き、悲しみに心が震えていくようだ。
恐らくもう二度と須江長の国に戻ることはないのでしょう。
嫁ぐ身であった時点で分かり切っていたことなのに、心の何処かで再び須江長の地へ足を踏み入れる事を望んでいたなんて。
このような場面になって今更気づかされてしまった。
どうする事もできない己の無力さ。足掻く気力さえもう残っていない。
心残りはないと言ったら嘘になる。けれどあの時の二の舞にならなかった事だけがせめてもの救いだ。
……さようなら、皆。有難う。
「行くぜ、野郎共!!!」
『おーーーー!!!』
森の奥深くに向かって男たちの声が木霊していった。
「そろそろ別れの時間だ」
そのまま腰に腕を回され俵担ぎにされ体が宙に浮く。
「舌を噛まないように気を付けろよ」
そう言って駆け出した重祢の言葉を人質として守って舌を奥へと引っ込める。
まるで走馬灯のように御輿やじぃ達が居る場所が段々と遠くなっていく。
規則的な振動が脳髄に響き、悲しみに心が震えていくようだ。
恐らくもう二度と須江長の国に戻ることはないのでしょう。
嫁ぐ身であった時点で分かり切っていたことなのに、心の何処かで再び須江長の地へ足を踏み入れる事を望んでいたなんて。
このような場面になって今更気づかされてしまった。
どうする事もできない己の無力さ。足掻く気力さえもう残っていない。
心残りはないと言ったら嘘になる。けれどあの時の二の舞にならなかった事だけがせめてもの救いだ。
……さようなら、皆。有難う。
「行くぜ、野郎共!!!」
『おーーーー!!!』
森の奥深くに向かって男たちの声が木霊していった。