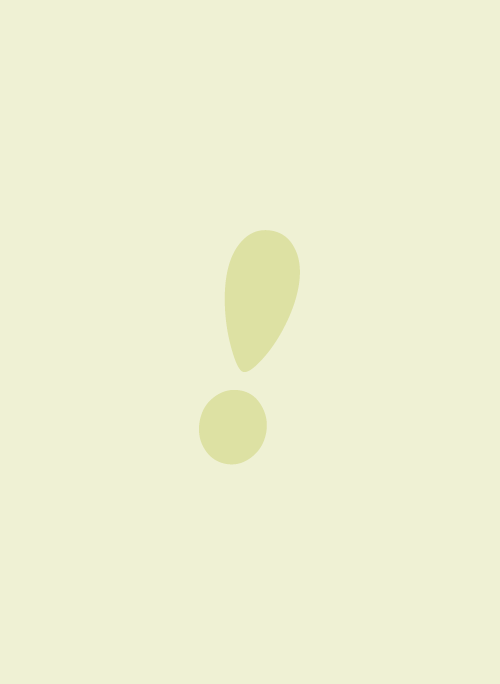「高屋くん、暇なら手伝って」
と、誰かが声をかけてきた。その声色は、ちょっとばかり勇気を必要とされただろう、上擦った声だった。
視線を向けると、彼女達は『のれん』を作っていた。紫色の大きな生地を裁断していて、傍らにはミシンが待機している。
僕は当然、気付いていた。
もちろん僕を必要としているワケではない。一人でいる僕を気遣っているのだ、と。
やれやれ、何で皆、こう優しいのだろう?
僕は当惑してしまう。
僕は微笑んで辞退を示すと、たまらず教室を出た。
と、誰かが声をかけてきた。その声色は、ちょっとばかり勇気を必要とされただろう、上擦った声だった。
視線を向けると、彼女達は『のれん』を作っていた。紫色の大きな生地を裁断していて、傍らにはミシンが待機している。
僕は当然、気付いていた。
もちろん僕を必要としているワケではない。一人でいる僕を気遣っているのだ、と。
やれやれ、何で皆、こう優しいのだろう?
僕は当惑してしまう。
僕は微笑んで辞退を示すと、たまらず教室を出た。