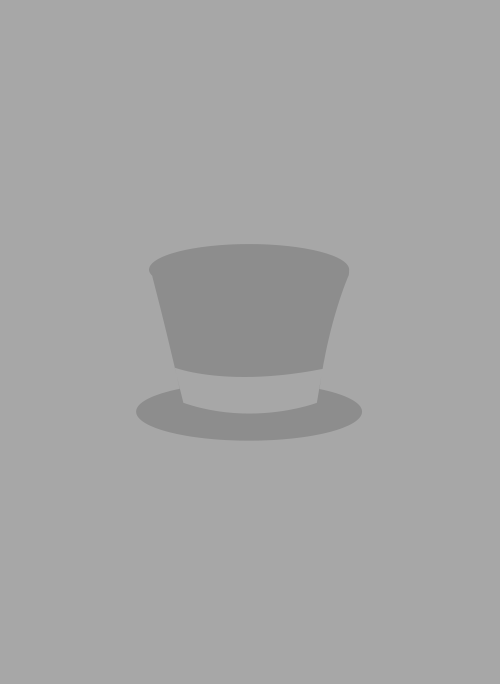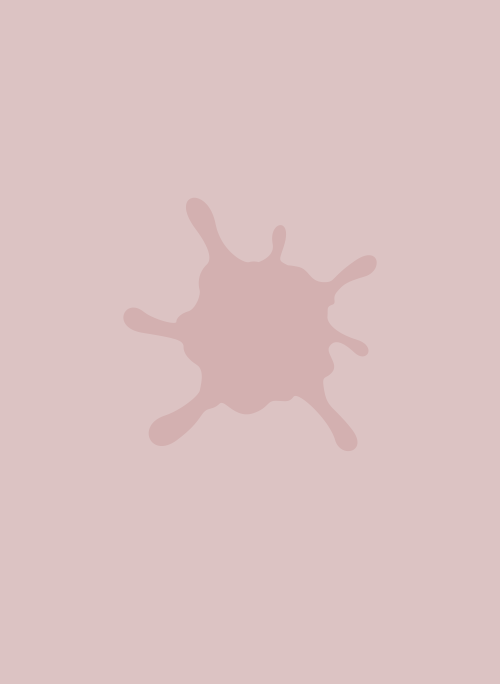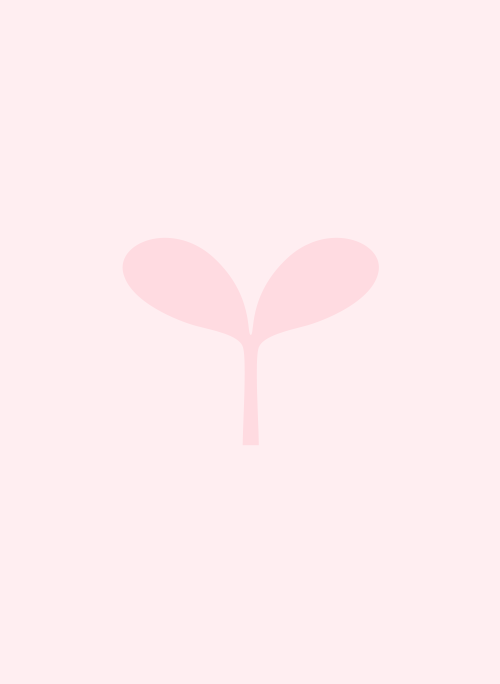まだ、私が特高の駆け出しであった頃、私の仕事と言えば、上から「赤」の疑いをかけられた者、臣民に良からぬ混乱を及ぼす危険性のある者、そう見なされた予備群およびその周囲の監視、観察、調査とゆう大義名分、名目の下、怨めしくも人を見張る仕事を担っておりました。
そんな折のこと(紫陽花が色彩を見せ始めて、周囲も私も嫌な季節の到来を予感し、すえ臭い雨合羽を物置戸から引き出し始めた折のこと)でした。
「小金井巡査!!」
ただ単に怒号であるか、私を差して呼んでいるか、定かではないほどの上沼巡査部長の号令があがりました。
格段、珍しいことではなく、それは幾度となく繰り返される日常ではあったのですが、私はそれにどうしても馴染むことが出来ず、その声を聞く度に肝が縮み上がるほどの思いでした。
そんな折のこと(紫陽花が色彩を見せ始めて、周囲も私も嫌な季節の到来を予感し、すえ臭い雨合羽を物置戸から引き出し始めた折のこと)でした。
「小金井巡査!!」
ただ単に怒号であるか、私を差して呼んでいるか、定かではないほどの上沼巡査部長の号令があがりました。
格段、珍しいことではなく、それは幾度となく繰り返される日常ではあったのですが、私はそれにどうしても馴染むことが出来ず、その声を聞く度に肝が縮み上がるほどの思いでした。