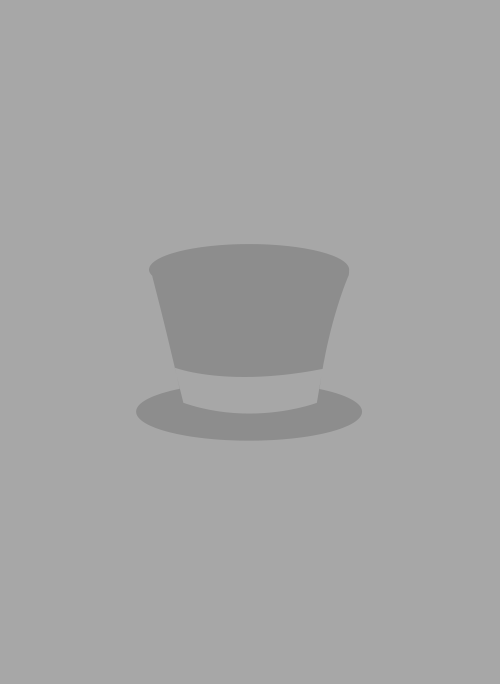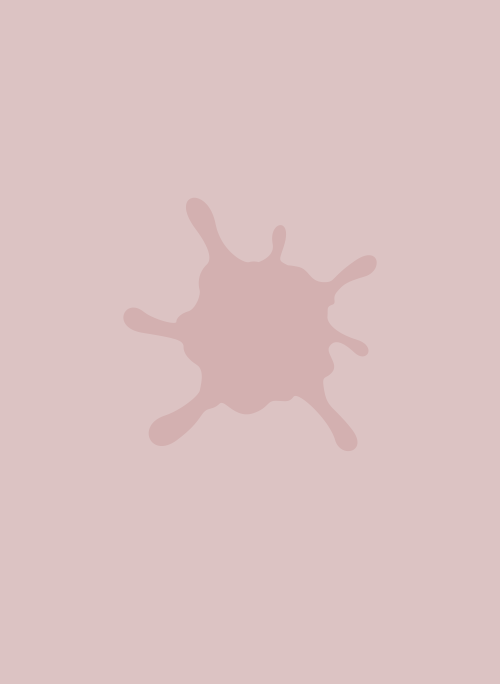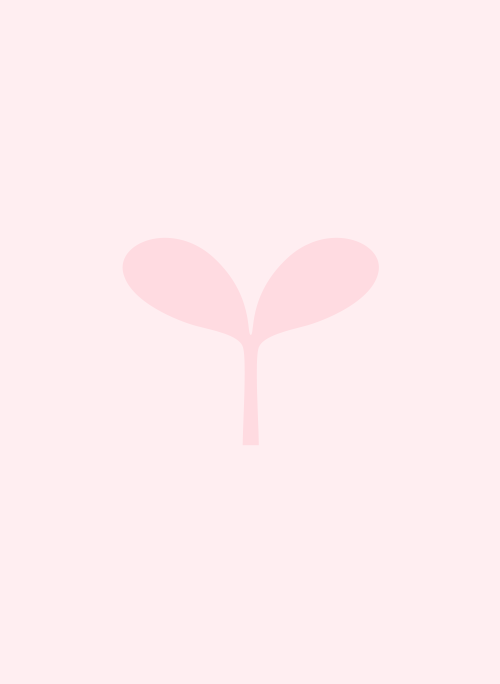まして、その忠義に対する疑惑なぞ、当時の私は皆目持ち合わせておりませんでした。
ただひたすらに、驕りと優越感を撒き散らし、子供が初めて与えられた玩具のように「赤」という言葉を連呼しては、徳のある方々を捕まえ、侮蔑に汚らわしい笑顔を浮かべておりました。
御国のため、天皇陛下のため、それを隠れ蓑にしては、無知で愚鈍な餓鬼たれは無邪気に遊びに耽っていたのです。
人の人生を大きく狂わせることなぞ、全く意識などせずに。
私のそうした行為を、遊びと表現するにはあまりに残酷な次第でありますが、忠義心すら通しきれない半端者の私では、どこまでも愚民の底の底を、進んでいたに違いないのです。
そんな私の心がざわつき、思想と精神を追究する学び舎に足を踏み入れることが出来た切っ掛けは、紛れもなく柊子さんとの出会いでありました。
ただひたすらに、驕りと優越感を撒き散らし、子供が初めて与えられた玩具のように「赤」という言葉を連呼しては、徳のある方々を捕まえ、侮蔑に汚らわしい笑顔を浮かべておりました。
御国のため、天皇陛下のため、それを隠れ蓑にしては、無知で愚鈍な餓鬼たれは無邪気に遊びに耽っていたのです。
人の人生を大きく狂わせることなぞ、全く意識などせずに。
私のそうした行為を、遊びと表現するにはあまりに残酷な次第でありますが、忠義心すら通しきれない半端者の私では、どこまでも愚民の底の底を、進んでいたに違いないのです。
そんな私の心がざわつき、思想と精神を追究する学び舎に足を踏み入れることが出来た切っ掛けは、紛れもなく柊子さんとの出会いでありました。