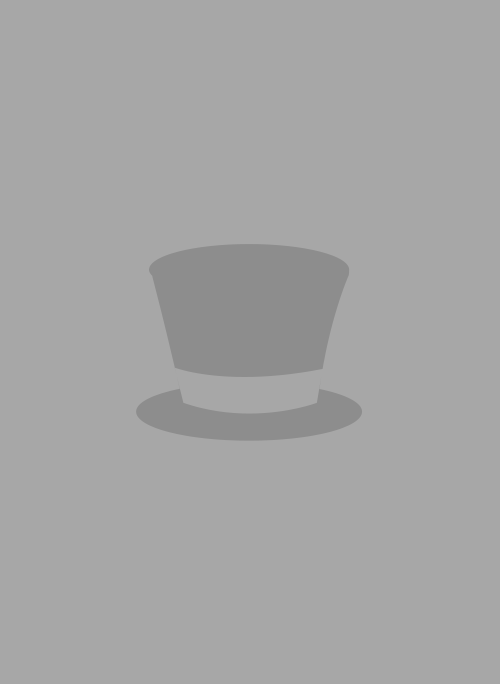「肴も直ぐに出来るよ」
フライパンが程好く焼けている。私は棚からオリーブオイルを取り出してフライパンに注ぎニンニクを入れて軽く炙り、茄子・玉葱・海老を塩・コショウで軽く炒め、豆板醤を放り込み絡ませる。徐々に海老と野菜に火が通り良い匂いが漂う。
「濃厚な味の酒にパンチの効いた肴か。こりゃ、今日はヘベレケに成る迄酔わすつもりやな」
「こう云う肴、好きだろう?」
「濃い味は大好きやで」
皿に乱暴に酒の肴を盛りカウンターに出す。普通の客相手には出来無い芸当だ。
「しかし、時雨と付き合いが出来て五年やけど、もっと昔から知っている様な不思議な錯覚を味わうな。不意に鋭い眼付きに成る時なんかは、恐ろしくて小便チビリそうに成るわ」
「私が絡まれている時に救いの手を差し伸べたのが和さんだよ。私の弱さは知っている筈だ」
「そう云えば、そんな事もあったな」
「腕に自信が無いからね。怖くて震えていたよ」
「ワシも腕には自信無いで。あるのは口先だけや」
「それも立派な防衛方法だよ。和さんの得意な口先のお陰で、今、私はこうして生きていられるからね」
関が私の言葉を受けて豪快に笑い出し、タンブラーの酒を飲むと、肴を摘み出す。私はそんな関を横目に煙草に火を点けて友人を眺める。この街から車で少し行った所に、関の生業で有る事務所の「自然・科学・心理学研究所」と云う屋号を上げた胡散臭い事務所が在ると云っていた。本人曰く依頼人も多く忙しいとの事だが、私の店に通う時は毎日の様に来るのを考えると、甚だ怪しい物だ。どんな商売にも波と云う物は有るが、関の事務所の屋号を考えると、本線の仕事が良く分から無い事もあり、私が依頼者なら間違い無く依頼先の対象から外しているだろう。別段、私と関は互いの過去を知り尽くしている訳では無い。そう云った意味では、私の知ら無い闇の部分が有るのかも知れない。だが、誰しもが人に云えない過去の一つや二つは有る物だ。私自身、人に明かせ無い過去が有るのだから。
「これ美味いな」
フライパンが程好く焼けている。私は棚からオリーブオイルを取り出してフライパンに注ぎニンニクを入れて軽く炙り、茄子・玉葱・海老を塩・コショウで軽く炒め、豆板醤を放り込み絡ませる。徐々に海老と野菜に火が通り良い匂いが漂う。
「濃厚な味の酒にパンチの効いた肴か。こりゃ、今日はヘベレケに成る迄酔わすつもりやな」
「こう云う肴、好きだろう?」
「濃い味は大好きやで」
皿に乱暴に酒の肴を盛りカウンターに出す。普通の客相手には出来無い芸当だ。
「しかし、時雨と付き合いが出来て五年やけど、もっと昔から知っている様な不思議な錯覚を味わうな。不意に鋭い眼付きに成る時なんかは、恐ろしくて小便チビリそうに成るわ」
「私が絡まれている時に救いの手を差し伸べたのが和さんだよ。私の弱さは知っている筈だ」
「そう云えば、そんな事もあったな」
「腕に自信が無いからね。怖くて震えていたよ」
「ワシも腕には自信無いで。あるのは口先だけや」
「それも立派な防衛方法だよ。和さんの得意な口先のお陰で、今、私はこうして生きていられるからね」
関が私の言葉を受けて豪快に笑い出し、タンブラーの酒を飲むと、肴を摘み出す。私はそんな関を横目に煙草に火を点けて友人を眺める。この街から車で少し行った所に、関の生業で有る事務所の「自然・科学・心理学研究所」と云う屋号を上げた胡散臭い事務所が在ると云っていた。本人曰く依頼人も多く忙しいとの事だが、私の店に通う時は毎日の様に来るのを考えると、甚だ怪しい物だ。どんな商売にも波と云う物は有るが、関の事務所の屋号を考えると、本線の仕事が良く分から無い事もあり、私が依頼者なら間違い無く依頼先の対象から外しているだろう。別段、私と関は互いの過去を知り尽くしている訳では無い。そう云った意味では、私の知ら無い闇の部分が有るのかも知れない。だが、誰しもが人に云えない過去の一つや二つは有る物だ。私自身、人に明かせ無い過去が有るのだから。
「これ美味いな」