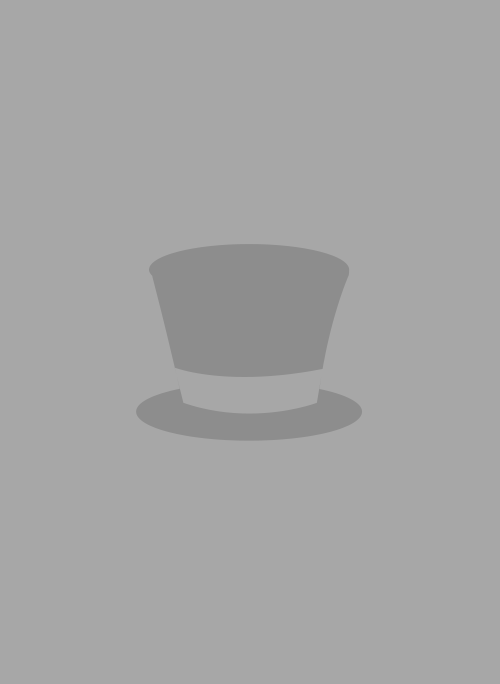「着いたで」
カーナビが目的地に着いたと音声で知らせて来る。私は静かにシートを起こすと、関がホットの缶コーヒーを差し出して来る。
「眠気覚ましや」
何時の間に缶コーヒーを買ったのか、それすらも気が付かない程に寝ていたのか。時計を見ると二十三時三十分を回っている。
「頂くよ」
掌に広がる温もりが心地良い。缶コーヒーの蓋を開けて一口飲む。ほろ苦い味が頭を覚醒させて行く。薬の作用の御蔭か、気分の悪さは無くスッキリとした気分だ。
「薬は抜けたんとちゃうか?」
「御蔭様でね」
「何年薬漬けに成ってか知らんけど、気分は如何や?」
「すこぶる良い」
「仕事は出切るか?」
「大丈夫だ」
「そうか。ワシは只見守るだけや。自分の仕事は、自分で始末を付けるんやで」
「分かっているよ」
思い切りコーヒーを飲み、缶をジュースフォルダーに置き、ドアを開けて外に出る。
「さっむいなぁ」
「今日は冷え込むな」
粉雪がひらひらと舞い降りて来る。田中夫妻の人生の幕引きには最高の晴れ舞台だ。路地の裏。私達は車から降りて、皮の手袋をして、紙片に書かれた住所に向って地図を片手に歩いて行く。小道。何度か路地を曲がりくねって歩いていると、一軒の長屋にぶち当たった。表札には田中陽一郎・梅子と記載されている。この家に間違いは無い。私達は静かに目配せをしてドアに手を掛ける。ガラリと、乾いた音がドアから響き、薄闇の玄関に入りドアを閉める。
饐えた匂いが鼻腔を擽る。靴を脱ぎ引き戸のドアを開ける。豆電球が部屋の中を薄っすらと照らし出している。
「来たか?」
部屋の中央。二人の老夫婦が横たわり、その手前に坂部が座っている。
カーナビが目的地に着いたと音声で知らせて来る。私は静かにシートを起こすと、関がホットの缶コーヒーを差し出して来る。
「眠気覚ましや」
何時の間に缶コーヒーを買ったのか、それすらも気が付かない程に寝ていたのか。時計を見ると二十三時三十分を回っている。
「頂くよ」
掌に広がる温もりが心地良い。缶コーヒーの蓋を開けて一口飲む。ほろ苦い味が頭を覚醒させて行く。薬の作用の御蔭か、気分の悪さは無くスッキリとした気分だ。
「薬は抜けたんとちゃうか?」
「御蔭様でね」
「何年薬漬けに成ってか知らんけど、気分は如何や?」
「すこぶる良い」
「仕事は出切るか?」
「大丈夫だ」
「そうか。ワシは只見守るだけや。自分の仕事は、自分で始末を付けるんやで」
「分かっているよ」
思い切りコーヒーを飲み、缶をジュースフォルダーに置き、ドアを開けて外に出る。
「さっむいなぁ」
「今日は冷え込むな」
粉雪がひらひらと舞い降りて来る。田中夫妻の人生の幕引きには最高の晴れ舞台だ。路地の裏。私達は車から降りて、皮の手袋をして、紙片に書かれた住所に向って地図を片手に歩いて行く。小道。何度か路地を曲がりくねって歩いていると、一軒の長屋にぶち当たった。表札には田中陽一郎・梅子と記載されている。この家に間違いは無い。私達は静かに目配せをしてドアに手を掛ける。ガラリと、乾いた音がドアから響き、薄闇の玄関に入りドアを閉める。
饐えた匂いが鼻腔を擽る。靴を脱ぎ引き戸のドアを開ける。豆電球が部屋の中を薄っすらと照らし出している。
「来たか?」
部屋の中央。二人の老夫婦が横たわり、その手前に坂部が座っている。