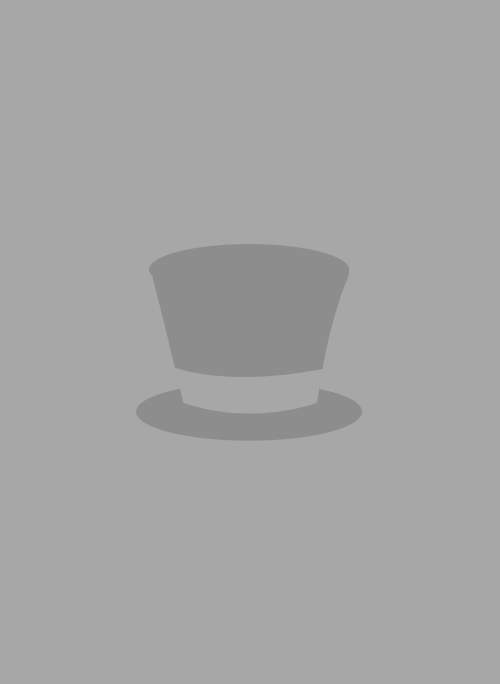三十路を迎えた平凡なサラリーマン。私の表社会の顔は、働いている職場こそ胡散臭いが、何処にでも居る有り触れたサラリーマンだ。雑踏の中。私は他のサラリーマンの例に習い、七階建ての雑居ビルのエレヴェーターに乗り、非常階段を開けて目的の店の前に立つ。プレハブの掘っ立て小屋。その建物の前に薄水色の看板。その爽やかな電飾に彩られた看板の中心部に、毒々しい赤の文字で『空』と云う文字が浮かんでいる。
「開いているかい?」
重々しい扉を開け店の中に声を掛ける。何時もの儀式。私は薄暗い照明に照らさせる店内に身体を滑り込ませて扉を閉める。
「あら、朴念仁がご出勤?」
「常連客に向けて喋る言葉じゃ無いね」
カウンターだけのスナック。私は、誰も居ない店内の中心分に陣取り、スツールに腰を下ろす。
「今日はこれでも飲みなさい」
カウンターの上。ママで有る袴田空子が御絞りを手渡すと、有無を云わさぬ口調で酒の用意をする。
「何を飲ましてくれるんだい?」
「ロイヤル・ロッホナガ。ザ・スコッチ・モルト・ウィスキー・ソサエティから届いた酒よ」
「開いているかい?」
重々しい扉を開け店の中に声を掛ける。何時もの儀式。私は薄暗い照明に照らさせる店内に身体を滑り込ませて扉を閉める。
「あら、朴念仁がご出勤?」
「常連客に向けて喋る言葉じゃ無いね」
カウンターだけのスナック。私は、誰も居ない店内の中心分に陣取り、スツールに腰を下ろす。
「今日はこれでも飲みなさい」
カウンターの上。ママで有る袴田空子が御絞りを手渡すと、有無を云わさぬ口調で酒の用意をする。
「何を飲ましてくれるんだい?」
「ロイヤル・ロッホナガ。ザ・スコッチ・モルト・ウィスキー・ソサエティから届いた酒よ」