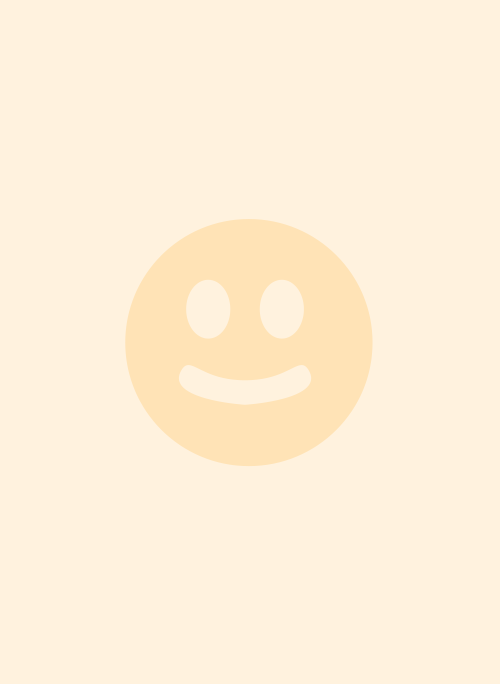「生憎、俺はこれ以上望まれても困るし、それを叶えてやれない」
そう言い放つ悠里の瞳は、今まで見たことがないくらい怖くて哀しそうだった。
「悠里……っ」
悠里は扉を開けて、皮肉たっぷりに笑ってみせる。
「その“お優しい安堂クン”に、ヨロシク」
いつもなら、「生意気」とか言ってキス一つして終わりだ
でも、見慣れたはずの広い背中は、とても冷たくて───遠かった。
あたしはドコで間違えたの?
ただただ、悠里に見てほしくて一心不乱だった。
遠くで悠里を呼ぶ女の子の声がして、いつもの“宮村センセイ”の声も後に続く。
──何も伝わらなかった。
がんばって伝えたのに、悠里には届かなかった。
崩れ落ちるように、床にへたり込んでしまったあたしは、たった一人で嗚咽を殺してあふれる涙をこらえるのに必死だった。
「美波、ちゃん……?」
静かに扉をあけたのは、安堂くんだった。
目が合って、どうしてだか、更に涙がこぼれた。
安堂くんは何も言わず、あたしの背中をさすり続けてくれた。
小さな教室に響く空調の音が、やけに耳障りだった───
.
そう言い放つ悠里の瞳は、今まで見たことがないくらい怖くて哀しそうだった。
「悠里……っ」
悠里は扉を開けて、皮肉たっぷりに笑ってみせる。
「その“お優しい安堂クン”に、ヨロシク」
いつもなら、「生意気」とか言ってキス一つして終わりだ
でも、見慣れたはずの広い背中は、とても冷たくて───遠かった。
あたしはドコで間違えたの?
ただただ、悠里に見てほしくて一心不乱だった。
遠くで悠里を呼ぶ女の子の声がして、いつもの“宮村センセイ”の声も後に続く。
──何も伝わらなかった。
がんばって伝えたのに、悠里には届かなかった。
崩れ落ちるように、床にへたり込んでしまったあたしは、たった一人で嗚咽を殺してあふれる涙をこらえるのに必死だった。
「美波、ちゃん……?」
静かに扉をあけたのは、安堂くんだった。
目が合って、どうしてだか、更に涙がこぼれた。
安堂くんは何も言わず、あたしの背中をさすり続けてくれた。
小さな教室に響く空調の音が、やけに耳障りだった───
.