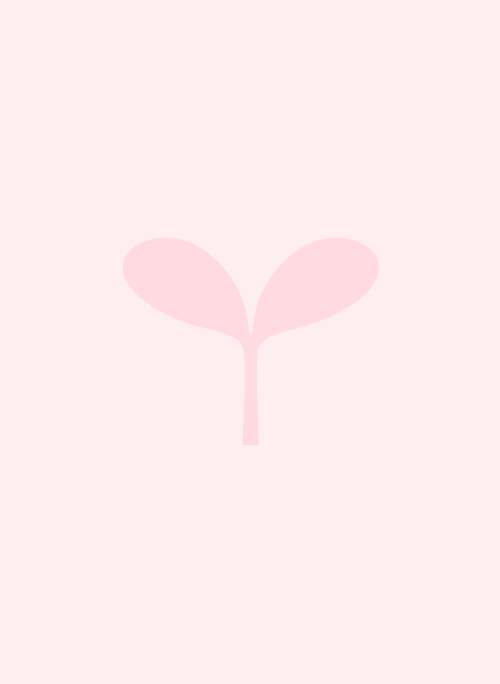――――――
あの日以来、スティークがラナに何かを言うことはなかった。
もしかしたら、というラナの期待も日に日に薄れはじめ、逆にエバンに対する申し訳なさが溢れてきていた。
あの日、スティークが自分を奪い去ってくれればと思った日、ラナは全てを捨ててスティークと共に生きるつもりだった。
しかし、スティークは何も言ってはくれなかった。
逆に、後日謝罪に行った時のエバンの優しさに、ラナは胸が締め付けられそうだった。
「エバンさんなら…私を愛してくれるのかしら…」
ぽつりと、ラナの口から零れた言葉。
その言葉を拾い上げてくれたのは、他でもない…
「愛しますよ」
エバンその人だった。