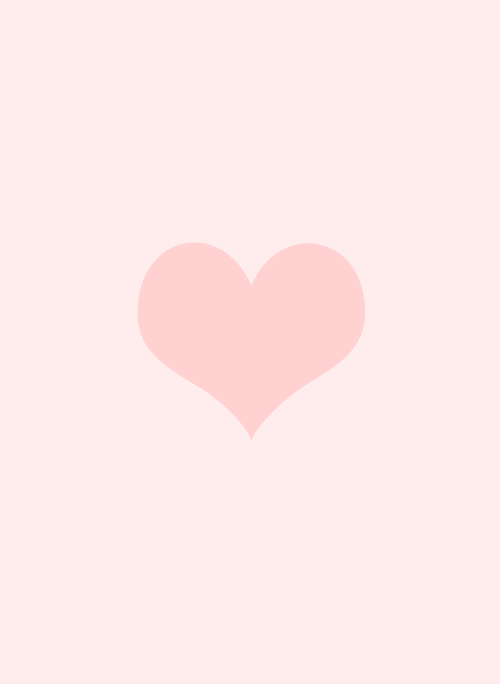「あ…雨音…。」
「体調…悪いの?」
「んなことない。だいじょーぶだいじょーぶ。」
「…顔赤いし…フラフラしてる。
保健室行くの?」
「少し休みに行くだけだから。」
「…私も行く。」
「え?」
…今のは幻聴?
だっておかしいだろ?
あの雨音が…保健室の付き添い?
「昨日傘を貸してくれたお礼に。」
そう言った彼女の表情は確かに無表情だった。
だけどその奥には…
あ、もちろん俺の思い違いの可能性大だけれど、少しだけ心配してくれているような気持があるようにも感じた。
…彼女は決して『冷たく』なんかない。
ただ…見せていないだけ。その優しさを、想いを。
もしかしたら、見ようとしていないだけなのかもしれない。
フラフラする俺の右腕が不意に掴まれる。
「え…?」
「危ないから。」
保健室まで、俺たちにそれ以上の会話はなかった。
「体調…悪いの?」
「んなことない。だいじょーぶだいじょーぶ。」
「…顔赤いし…フラフラしてる。
保健室行くの?」
「少し休みに行くだけだから。」
「…私も行く。」
「え?」
…今のは幻聴?
だっておかしいだろ?
あの雨音が…保健室の付き添い?
「昨日傘を貸してくれたお礼に。」
そう言った彼女の表情は確かに無表情だった。
だけどその奥には…
あ、もちろん俺の思い違いの可能性大だけれど、少しだけ心配してくれているような気持があるようにも感じた。
…彼女は決して『冷たく』なんかない。
ただ…見せていないだけ。その優しさを、想いを。
もしかしたら、見ようとしていないだけなのかもしれない。
フラフラする俺の右腕が不意に掴まれる。
「え…?」
「危ないから。」
保健室まで、俺たちにそれ以上の会話はなかった。