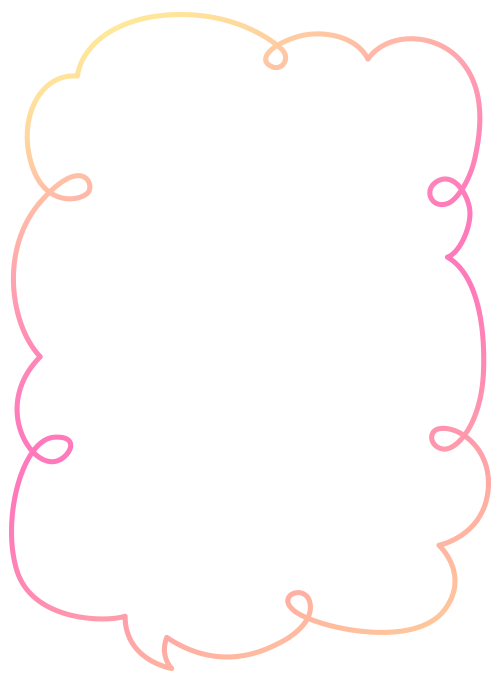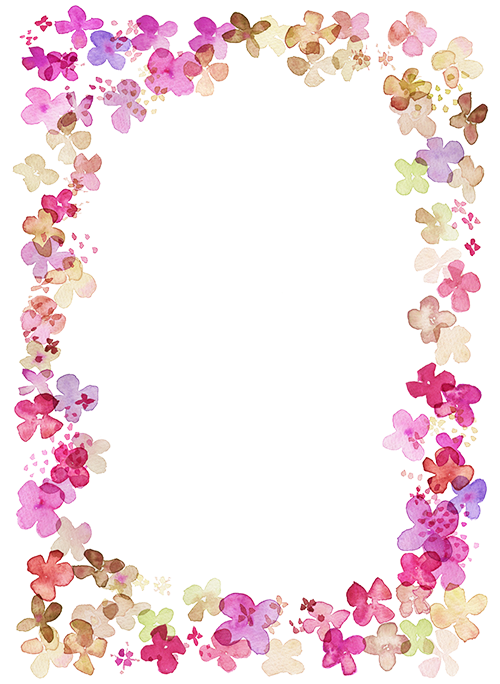「ねぇねぇ、小野君」
バイクに乗るのは生まれて初めての経験だった。
スピード感も風を切って走る爽快感も、自転車とはまるで違う。
って、自転車と比べちゃダメか。
小野君の背中にペタッとくっ付いてボソボソ呟いても、うるさいエンジン音にかき消されて小野君には聞こえない。
「小野君の背中温かいよ……。ずっとこのままがいいなぁ」
小野君のお腹に回している腕がジンジンと痺れてくる。
顔を大きな背中にくっつけると小野君の体温が直接顔に届いた。
温かくて心地いい小野君の熱をこのままずっと感じていたい。
「……いい匂い」
あたしは目を瞑り、小野君の甘い香水の匂いに胸を高鳴らせていた。