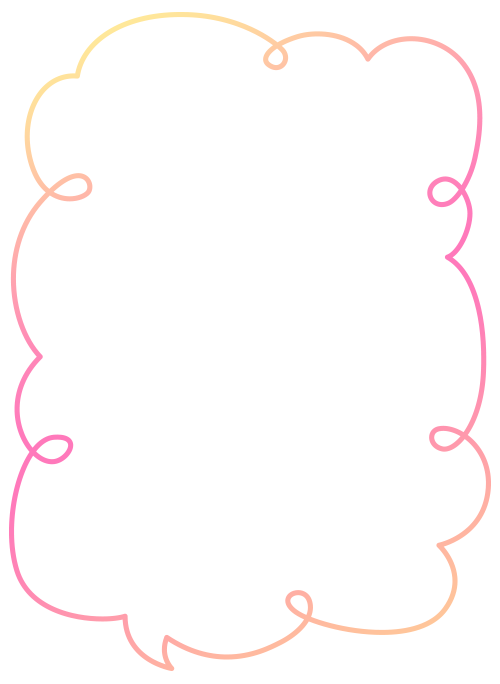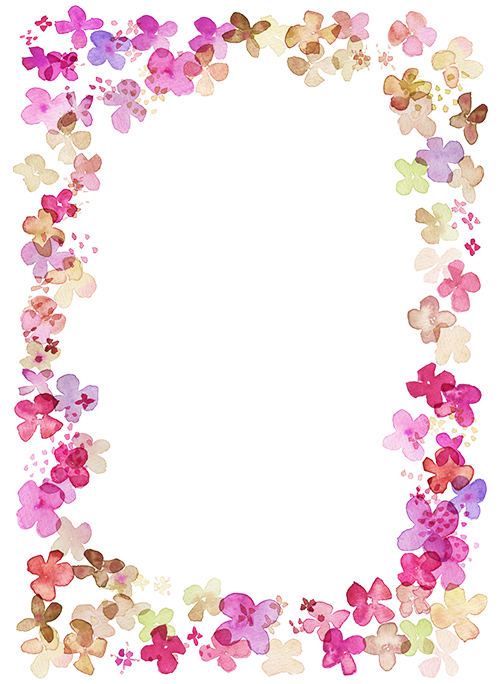その手をあたしが掴むと、小野君は再び歩き出した。
ねぇ、小野君。
あたしはこの先何があっても、この手だけは絶対に離したくないよ。
「小野君……ずっとあたしの隣にいてね?」
「あぁ。お前が離れていかない限り、ずっと隣にいてやるよ」
小野君のその言葉には最大級の愛が込められているような気がして。
「……小野君、好きだよ?」
そう呟くと、小野君は繋いだ手にギュッと力を込めた。
「あ、ねぇ。最後にもう一回聞くけど、本当に誕生日プレゼントは……――」
家に着く直前。あたしは小野君の顔を覗き込みながらそう聞いた。
一生に一度しかない17歳の誕生日。
あたし、小野君に何もあげてない。
すると小野君はチラッと横目であたしを見た。
「もう、もらった」
「え?何を?あたし、小野君に何もあげてないよ??」
プレゼントもケーキも……何も……。
「俺にとって、お前が最高のプレゼントだから」
あたしが……最高のプレゼント?
それってもしかして……
「あたし……の……体?!」
それしかないよね?!もう!!小野君ってば!!
一人で興奮するあたしを横目に小野君は眉をしかめる。
「いちいち口に出すなよ。つーか、その言い方じゃ、俺がお前の体目当てだって言ってるようなもんだろ?」
「か、体目当てだったの?!」
「お前の体だけが目当てだったら、ラブホ行った時に、無理矢理ヤったに決まってんだろ?」
小野君はそう言うと、照れ臭そうに顔を背ける。
小野君に『お前が最高のプレゼント』と言われたあたしは、家に着くまでの間、ずっとニヤけっぱなしだった。