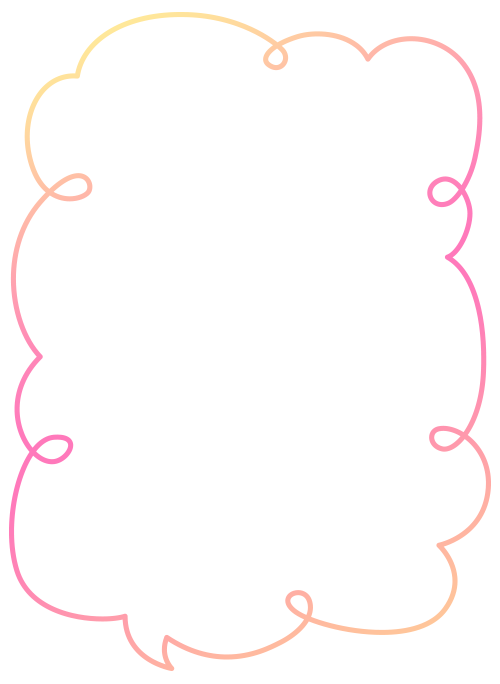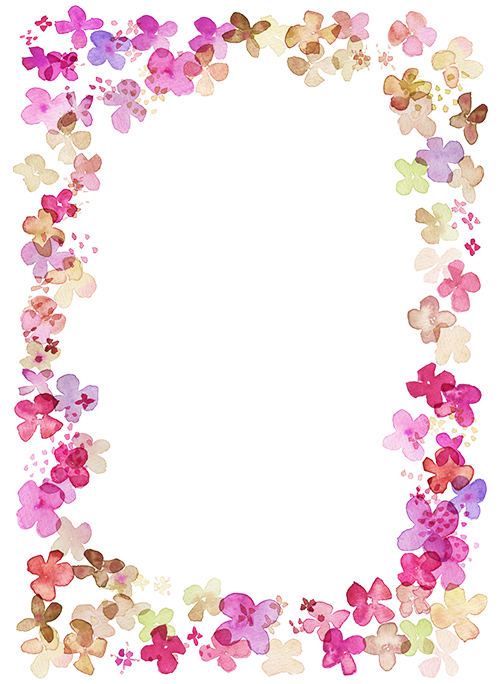「相手が一人でもカップルでもお構いなしらしいし、かなりヤバいね。聞いた話だと、カップルの男にボコボコにされても嬉しそうに笑ってたみたい」
「そうなんだ……。小野君がいてくれてよかったぁ」
昨日小野君が一緒に帰ってくれなければ、あたしは一人で恐怖に怯えていただろう。
「……え?何それ?小野君が一緒の時に不審者に遭遇したの?」
すると、突然舞子が不思議そうな顔で首を傾げた。
「そうだけど……どうして?」
「どうしても何も、二人が学校外で一緒にいるなんて信じられない!」
「あたしも信じられないんだけど、昨日、家まで送っていってもらったの。小野君に」
『小野君に』の部分を強調して答えると、舞子は目を丸くした後、声を張り上げた。
「……――えぇ?!そうだったの?!」
「ちょっと、舞子!驚きすぎだってば!!」
「へぇ~……、何だかんだいって小野君もアユのこと気にかけてんのね!!」
舞子はニッと笑って「よかったねぇ~」と言いながらあたしの頭をポンポンッと叩いた。