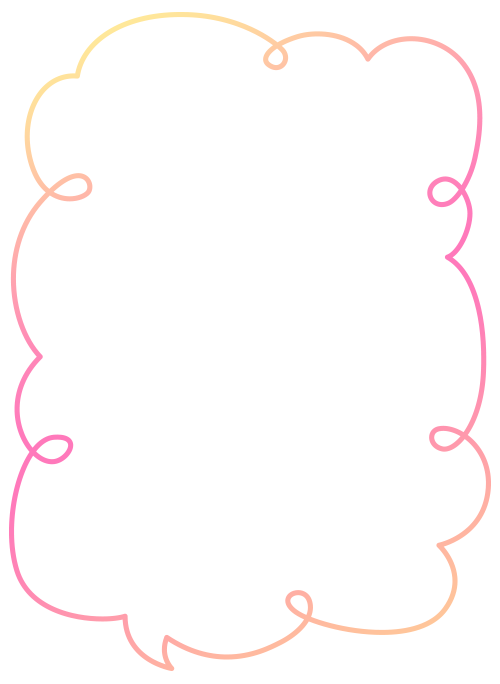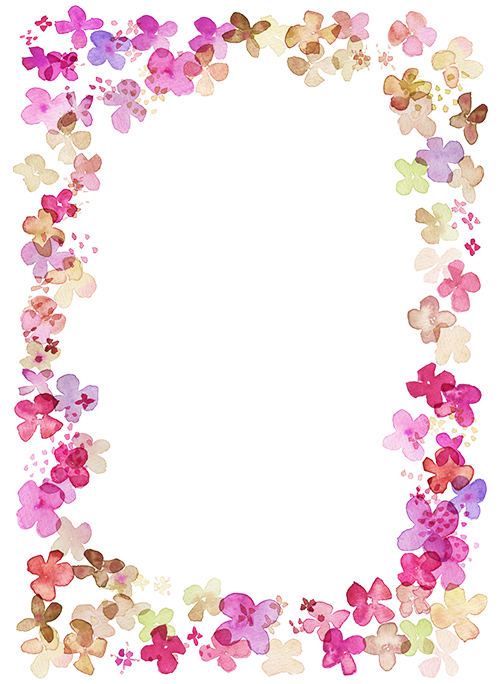「だからね、あたしは小野君のさりげない優しさが好きなの!」
もしこれで分からないと言われたらどうしよう。
そんな心配をしたけど、小野君は聞き返してこなかった。
その代わりに、何故か小野君はプイッとあたしから顔を背ける。
「……おーい、小野君?」
「……んだよ」
その横顔が少しだけ赤くなった気がするのは、きっと目の錯覚だ。
だって、辺りは真っ暗だし小野君の顔が赤いなんて分かるわけないもん。
だけど、どうしてだろう。
あたしが「好き」って言った途端に小野君が顔を反らすなんて。
……もしかして、小野君……あたしに「好き」って言わせようとしてた?
そんな……まさかね。
「ねぇねぇ、小野君……――」
調子に乗って小野君の袖をクイクイッと引っ張る。
すると小野君はパッとあたしの手を掴んだ。
「前見て歩け」
「へ?」
小野君の言葉にハッと我に返る。
目の前には一本の電柱。
「あ、ごめん!!ありがとう」
慌ててお礼を言うと、小野君はあたしの頭をポンッと叩いた。
「お前、危なっかしいんだよ。俺から離れんな」
小野君の言葉がグルグルと頭の中を回る。
「……離んなって……どうすればいいのかな?」
小野君に自分からくっつける度胸もない。
だからと言って、小野君は離れるなって言うし……。
「こうしてればいいんだよ」
すると、小野君はあたしの腰をグイッと自分の体に引き寄せた。
小野君の体とあたしの体がピタッと密着する。
息が止まりそうなほど驚いて口をパクパクと開ける。
あたしは小野君に30センチ以上近付くと、心臓が爆発しちゃうんだ。
心臓がバクバクと暴れ出して、全身が熱を帯びる。
「お、お、小野君……」
「バカ面」
そんなあたしを見て、小野君はふんと余裕そうな笑みを浮かべた。