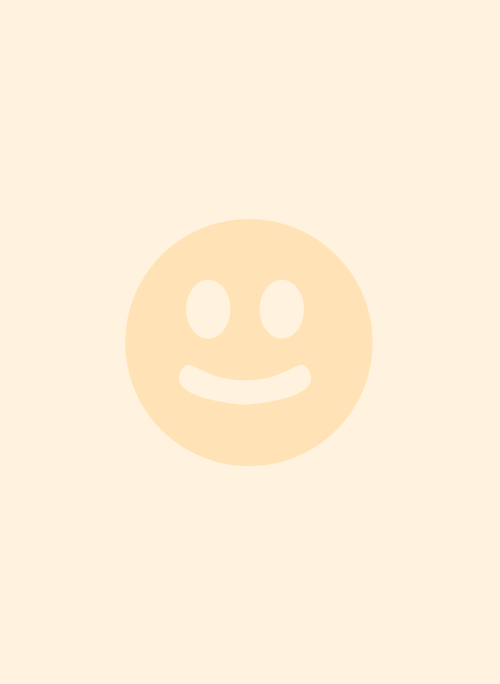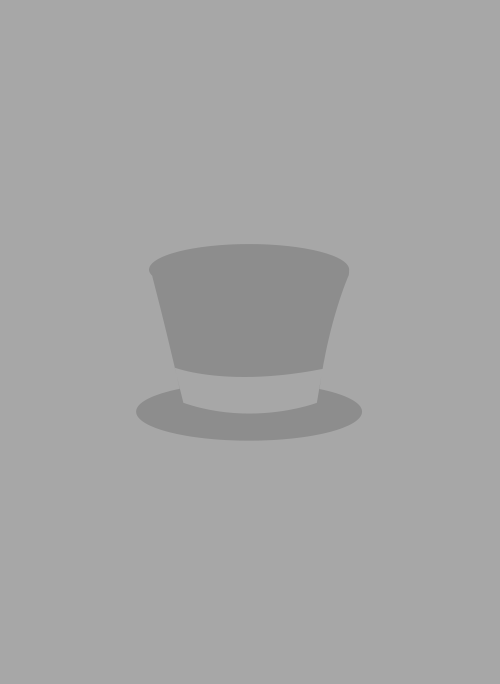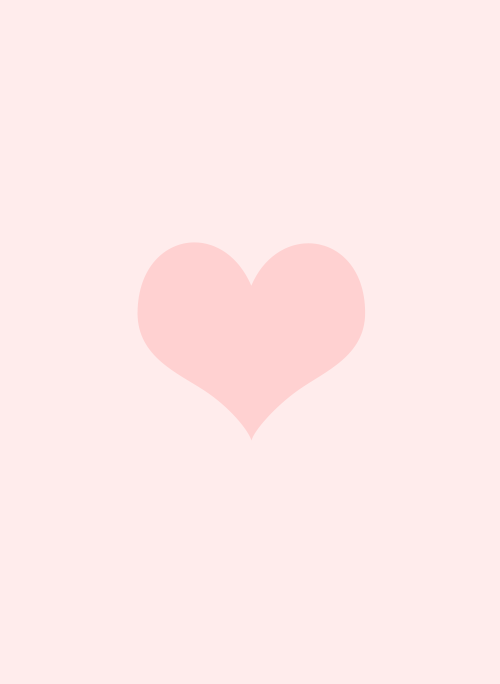「最低!」
私が言うと、ヒトシは深いため息をついた。
「すまない」
「謝って済む問題じゃないと思います」
「そうだよな」
「どうするんですか?」
「国外逃亡」
「罪を償ったりはしないんですか?」
「まあな」
「でも、外国に行っちゃったら、会えなくなっちゃうし、メールも電話も出来ないんですよね?」
「いや、外国だって、インターネットくらいあるよ……いや、僕の行くところは田舎だから、どうかな」
「どこに行くんですか?」
「また、農場だよ」
「農場?」
「ああ。僕、案外、搾乳とか向いてるみたいなんだ」
「乳牛!?」
「一日、牛の世話をしてさ、辛い仕事だけど、充実感があるんだ」
「牛の世話……!?」
「ああ、もちろん、米も作ると思う」
「水田ですか?」
「ああ。でも、日本とはやりかたが違うかもしれないな」
話しているうちに、私の頬は、涙で濡れていた。
こんなふうに、ヒトシと話すことが出来るのも、もう最後だ。
そう思うと、悲しくて、仕方が無かった。
「どんなお米を作るんですか?」
泣きじゃくりながら、私は言った。
「タイ米」
ガコン、
と、音を立てて、観覧車が再び動き出したのは、ヒトシがそう言ったと同時だった。