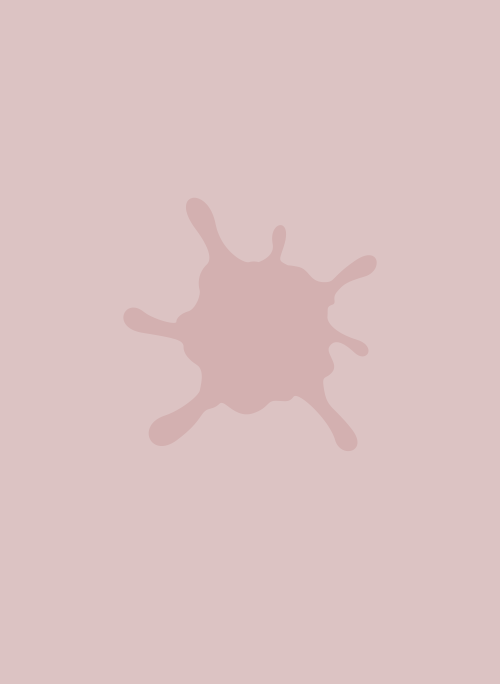「………」
太一達が居なくなり、緊張がとれたのか輝太は震えていた。
「大丈夫?輝太」
「!」
稀琉に声を掛けられた輝太はハッとして稀琉の方を向いた。心配そうにしている姿を見て慌てて返答する。
「稀琉お兄ちゃん…。ありがとう…大丈夫だよ」
「それなら良かった。それにしても……何なの!あの子たち!ちょっと失礼過ぎない!?」
太一達が消えていった道を見ながら稀琉は頬を膨らませながら怒っていた。稀琉は太一がボールを輝太に投げた時から様子が見えていた。慌てて向かうと今度はクロムに対しても暴言を投げかけていたのを聞いていたので、その事について怒っていたのだ。怒る稀琉の問いに小さな声で輝太答える。
「…太一くんはいっつもあんな感じなんだ」
「いつもなの!?その事、先生に言ってる?」
「…ううん。誰に対してもあんな感じだし、今日みたいに言われることはあまりないから…」
「駄目だよ!先生に言わないと!本当に言葉遣いとか、態度とか凄く嫌な感じだもん!クロムにも失礼な事言ってさ!オレ普段怒ることあんまりないけど流石に頭にきちゃった!クロムもそう思わない!?」
「!」
稀琉が愚痴を言う中、クロムの名前が出てきて輝太はハッとしたようにクロムの方を見た。
「…クソガキなんてあんなもんだろ。いちいち本気になんな」
本から目を逸らさず、面倒そうに答えるクロム。しかし、稀琉は納得できない様で言葉を続けた。
「でもさ!許せないよ!クロムは何もしてないのに!きもいって何!意味わかって言ってんの!?って言いたくなるよ!!それにクロムだって怒ったからボール蹴ったんでしょ!?」
「…でけぇ声出すな、うるせぇな。相手にすんなって言ってんだろ。俺はいつまでもあいつらが居て鬱陶しかったからさっさとご退場願ったまでだ。あんなクソガキ放っておけ」
「うー…でも…!」
「くどいぞ」
怒る稀琉とは対照的に、嫌な言葉を言われた筈の当人は何事もなかったかの様に振る舞っていた。きっとクロムの言葉通り、あそこで太一達がその場を立ち去れば何もする気がなかったのだろう。
(そうだ…。クロムお兄ちゃんが止めてくれなかったら…僕はきっと太一くんの事…いつもされているみたいに叩いてた…)
ギュッと唇を噛み締めた輝太は意を決してクロムに声を掛けた。
「あ…あの…クロムお兄ちゃん…」
「…なんだ」
「さっきは…ありがとう。僕…頭が真っ白になっちゃって……ごめんなさい」
「輝太……」
あからさまに落ち込んでいる輝太を見た稀琉の怒りが引っ込む。そんな輝太を横目で見たクロムは溜め息をついた。
「……別に。お前が自分の為にやってんなら止める道理はなかったが、どう見ても俺に対してあのクソガキが謝らなかったからやってたからな。稀琉もお前も俺の事で怒ってんなら、余計なお世話だ。俺はあんなクソガキ相手にしてねぇんだよ。ああいうのは無視しろ。相手にするとつけあがるぞ」
「……ごめんなさい。でも…どうしても許せなかったの…」
「……別にお前に怒って貰わんでも自分でやれる。俺は我慢しないんでな。さっきみたいに邪魔だったら追い出すとかな。頼んでねぇ事を勝手にすんな。迷惑だ」
「ちょっとクロム!そんな言い方…」
「お前は黙ってろ。…前に言っただろ。先を見据えて行動しろって。何度言わせる気だ。俺やこいつはともかくお前は明日からもあのクソガキと一緒に生活しねぇとなんないだろ。他人に気にかける前にまずは自分の事を考えろよ。それとやっちまった事に対していつまでもうじうじすんな。嫌いなんだよ、そういうの。分かったらさっさと遊んでこい」
「……ごめんなさい」
それだけ言うとクロムは本をコートのポケットに入れて立ち上がった。落ち込む輝太の横を気にも止めずに通り過ぎる。
「あ…」
声を掛けようと手を伸ばすがグッとその拳を握り締める。いつもと同じスピードで歩いているクロムの後ろ姿は、普段歩くスピードを合わせてもらっている輝太にとって“置いて行かれた”と思わせるものであった。
「ッ……」
下を向いて落ち込む輝太とクロムの後ろ姿を交互に見た稀琉は「もー…クロムは…」と呟きながら輝太の側に寄って行った。
「…輝太。ちょっとこっちにおいで」
「…うん」
稀琉は落ち込む輝太を連れて少し離れた場所に行った。そこは草原になっており、下を見ると川が流れている場所だった。夕暮れの太陽が水面でキラキラと輝いている。ふわりと花の香りと、楽しげな人々の声がする。
「……」
そんな楽しそうな雰囲気とは裏腹に輝太の表情は暗かった。稀琉は草原に座り、ゆっくりと口を開いた。
「…ねぇ輝太。確かに…叩こうとしてしまったのはいけない事だけど…オレは輝太が怒る理由も分かるし、クロムの為に怒れる輝太は凄いと思うよ」
「……でも、クロムお兄ちゃん…迷惑って言ってたよ…。勝手な事しないでって」
「クロムはさ…とってもお話が下手なんだよ。誰に対してもそうなんだ。でも…クロムが言いたかったのは「自分の為に輝太が辛い目にあって欲しくない」って事だと思うんだ。叩こうとする前に止めてくれたし、明日からの輝太が学校に行きづらくならないように言ってくれたんだよ」
「……僕…クロムお兄ちゃんの事、大好き。でも……また怒られちゃった…グス……。何回言わせるんだって…ヒック…嫌いだって…ズズッ…クロム…お兄ちゃんに…ヒック…嫌われたら……グスッ…どうしよう……」
人を叩こうとしてしまった事や何度も同じ事を言わせてしまった事…不安が爆発してしまった輝太は泣き始めてしまった。稀琉は泣いている輝太の背中を摩りながら川を見ていた。
「そうだね。さっきの言い方だと…不安になっちゃうよね。でも大丈夫だよ。…自分で言ってたでしょ?我慢しないって。それにね…輝太の事は気にかけてくれてると思うよ。だってオレなんか1年以上話もしてくれなかったんだから」
「え…?」
涙が溜まった瞳を稀琉に向ける。夕日に照らされている稀琉は変わらずに川を見ていた。
「少し前からなんだ。クロムがオレや麗弥と話してくれるようになったの。だから分かるよ。クロムがそのつもりなかったら…嫌ってたら話すらしてくれないって。でも輝太とはお話ししてくれるでしょ?」
「でも……クロムお兄ちゃん…帰っちゃったよ……」
「帰ってないから大丈夫。その内戻ってくるよ。口下手だけど…戻ったら変わらずに話してくれると思うから落ち込まないで」
「…稀琉お兄ちゃん……」
「それにほら。さっきの子…太一くんだっけ?あの子に対しては「クソガキ」って言ってたけど、輝太の事は名前で呼んでくれてるでしょ?その時点で少なくとも嫌いではないよ。クロムは面倒くさがりだから、もしもう嫌いなら…話してくれないと思うしね。名前だってオレと麗弥を呼んでくれたのも最近って言えば最近だし。だからきっと大丈夫」
「………」
涙が溜まる目で後方に居るクロムを見る。変わらず本を読んではいるが、その場に留まっている。
「…うん。ありがとう、稀琉お兄ちゃん」
「いいえ。さっ!涙を拭いて戻ろ」
「…うん!」
袖で涙を拭った輝太と稀琉は戻った。稀琉にはああ言われたものの、輝太の中に不安は残っていた。ベンチを見るもクロムの姿はない。やっぱり帰ってしまったのではないか、戻ってきても無視されるかもしれない、明日から来てくれなくなったらどうしよう…等、不安が駆け巡っていた。ズキズキとした痛みやドキドキと心臓が鳴っている中、稀琉と一緒にベンチに座る。稀琉は何も言わずに背中を摩っていた。そのお陰で多少安心感があるものの気が気でない中、ベンチに座って俯いていた時だった。
太一達が居なくなり、緊張がとれたのか輝太は震えていた。
「大丈夫?輝太」
「!」
稀琉に声を掛けられた輝太はハッとして稀琉の方を向いた。心配そうにしている姿を見て慌てて返答する。
「稀琉お兄ちゃん…。ありがとう…大丈夫だよ」
「それなら良かった。それにしても……何なの!あの子たち!ちょっと失礼過ぎない!?」
太一達が消えていった道を見ながら稀琉は頬を膨らませながら怒っていた。稀琉は太一がボールを輝太に投げた時から様子が見えていた。慌てて向かうと今度はクロムに対しても暴言を投げかけていたのを聞いていたので、その事について怒っていたのだ。怒る稀琉の問いに小さな声で輝太答える。
「…太一くんはいっつもあんな感じなんだ」
「いつもなの!?その事、先生に言ってる?」
「…ううん。誰に対してもあんな感じだし、今日みたいに言われることはあまりないから…」
「駄目だよ!先生に言わないと!本当に言葉遣いとか、態度とか凄く嫌な感じだもん!クロムにも失礼な事言ってさ!オレ普段怒ることあんまりないけど流石に頭にきちゃった!クロムもそう思わない!?」
「!」
稀琉が愚痴を言う中、クロムの名前が出てきて輝太はハッとしたようにクロムの方を見た。
「…クソガキなんてあんなもんだろ。いちいち本気になんな」
本から目を逸らさず、面倒そうに答えるクロム。しかし、稀琉は納得できない様で言葉を続けた。
「でもさ!許せないよ!クロムは何もしてないのに!きもいって何!意味わかって言ってんの!?って言いたくなるよ!!それにクロムだって怒ったからボール蹴ったんでしょ!?」
「…でけぇ声出すな、うるせぇな。相手にすんなって言ってんだろ。俺はいつまでもあいつらが居て鬱陶しかったからさっさとご退場願ったまでだ。あんなクソガキ放っておけ」
「うー…でも…!」
「くどいぞ」
怒る稀琉とは対照的に、嫌な言葉を言われた筈の当人は何事もなかったかの様に振る舞っていた。きっとクロムの言葉通り、あそこで太一達がその場を立ち去れば何もする気がなかったのだろう。
(そうだ…。クロムお兄ちゃんが止めてくれなかったら…僕はきっと太一くんの事…いつもされているみたいに叩いてた…)
ギュッと唇を噛み締めた輝太は意を決してクロムに声を掛けた。
「あ…あの…クロムお兄ちゃん…」
「…なんだ」
「さっきは…ありがとう。僕…頭が真っ白になっちゃって……ごめんなさい」
「輝太……」
あからさまに落ち込んでいる輝太を見た稀琉の怒りが引っ込む。そんな輝太を横目で見たクロムは溜め息をついた。
「……別に。お前が自分の為にやってんなら止める道理はなかったが、どう見ても俺に対してあのクソガキが謝らなかったからやってたからな。稀琉もお前も俺の事で怒ってんなら、余計なお世話だ。俺はあんなクソガキ相手にしてねぇんだよ。ああいうのは無視しろ。相手にするとつけあがるぞ」
「……ごめんなさい。でも…どうしても許せなかったの…」
「……別にお前に怒って貰わんでも自分でやれる。俺は我慢しないんでな。さっきみたいに邪魔だったら追い出すとかな。頼んでねぇ事を勝手にすんな。迷惑だ」
「ちょっとクロム!そんな言い方…」
「お前は黙ってろ。…前に言っただろ。先を見据えて行動しろって。何度言わせる気だ。俺やこいつはともかくお前は明日からもあのクソガキと一緒に生活しねぇとなんないだろ。他人に気にかける前にまずは自分の事を考えろよ。それとやっちまった事に対していつまでもうじうじすんな。嫌いなんだよ、そういうの。分かったらさっさと遊んでこい」
「……ごめんなさい」
それだけ言うとクロムは本をコートのポケットに入れて立ち上がった。落ち込む輝太の横を気にも止めずに通り過ぎる。
「あ…」
声を掛けようと手を伸ばすがグッとその拳を握り締める。いつもと同じスピードで歩いているクロムの後ろ姿は、普段歩くスピードを合わせてもらっている輝太にとって“置いて行かれた”と思わせるものであった。
「ッ……」
下を向いて落ち込む輝太とクロムの後ろ姿を交互に見た稀琉は「もー…クロムは…」と呟きながら輝太の側に寄って行った。
「…輝太。ちょっとこっちにおいで」
「…うん」
稀琉は落ち込む輝太を連れて少し離れた場所に行った。そこは草原になっており、下を見ると川が流れている場所だった。夕暮れの太陽が水面でキラキラと輝いている。ふわりと花の香りと、楽しげな人々の声がする。
「……」
そんな楽しそうな雰囲気とは裏腹に輝太の表情は暗かった。稀琉は草原に座り、ゆっくりと口を開いた。
「…ねぇ輝太。確かに…叩こうとしてしまったのはいけない事だけど…オレは輝太が怒る理由も分かるし、クロムの為に怒れる輝太は凄いと思うよ」
「……でも、クロムお兄ちゃん…迷惑って言ってたよ…。勝手な事しないでって」
「クロムはさ…とってもお話が下手なんだよ。誰に対してもそうなんだ。でも…クロムが言いたかったのは「自分の為に輝太が辛い目にあって欲しくない」って事だと思うんだ。叩こうとする前に止めてくれたし、明日からの輝太が学校に行きづらくならないように言ってくれたんだよ」
「……僕…クロムお兄ちゃんの事、大好き。でも……また怒られちゃった…グス……。何回言わせるんだって…ヒック…嫌いだって…ズズッ…クロム…お兄ちゃんに…ヒック…嫌われたら……グスッ…どうしよう……」
人を叩こうとしてしまった事や何度も同じ事を言わせてしまった事…不安が爆発してしまった輝太は泣き始めてしまった。稀琉は泣いている輝太の背中を摩りながら川を見ていた。
「そうだね。さっきの言い方だと…不安になっちゃうよね。でも大丈夫だよ。…自分で言ってたでしょ?我慢しないって。それにね…輝太の事は気にかけてくれてると思うよ。だってオレなんか1年以上話もしてくれなかったんだから」
「え…?」
涙が溜まった瞳を稀琉に向ける。夕日に照らされている稀琉は変わらずに川を見ていた。
「少し前からなんだ。クロムがオレや麗弥と話してくれるようになったの。だから分かるよ。クロムがそのつもりなかったら…嫌ってたら話すらしてくれないって。でも輝太とはお話ししてくれるでしょ?」
「でも……クロムお兄ちゃん…帰っちゃったよ……」
「帰ってないから大丈夫。その内戻ってくるよ。口下手だけど…戻ったら変わらずに話してくれると思うから落ち込まないで」
「…稀琉お兄ちゃん……」
「それにほら。さっきの子…太一くんだっけ?あの子に対しては「クソガキ」って言ってたけど、輝太の事は名前で呼んでくれてるでしょ?その時点で少なくとも嫌いではないよ。クロムは面倒くさがりだから、もしもう嫌いなら…話してくれないと思うしね。名前だってオレと麗弥を呼んでくれたのも最近って言えば最近だし。だからきっと大丈夫」
「………」
涙が溜まる目で後方に居るクロムを見る。変わらず本を読んではいるが、その場に留まっている。
「…うん。ありがとう、稀琉お兄ちゃん」
「いいえ。さっ!涙を拭いて戻ろ」
「…うん!」
袖で涙を拭った輝太と稀琉は戻った。稀琉にはああ言われたものの、輝太の中に不安は残っていた。ベンチを見るもクロムの姿はない。やっぱり帰ってしまったのではないか、戻ってきても無視されるかもしれない、明日から来てくれなくなったらどうしよう…等、不安が駆け巡っていた。ズキズキとした痛みやドキドキと心臓が鳴っている中、稀琉と一緒にベンチに座る。稀琉は何も言わずに背中を摩っていた。そのお陰で多少安心感があるものの気が気でない中、ベンチに座って俯いていた時だった。