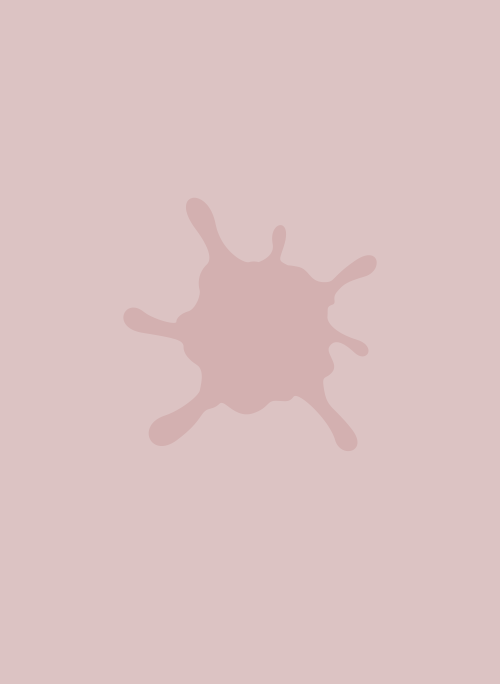でも、宮野君はそんな私の気持ちに気づくわけもない。
わかっている。
だって、その程度の関係なんだから。
ここで手を引いて、どうしてそんなことを言うのって言えない関係。
だから私は自分の悲しい気持ちをこらえるために唇を軽く噛んだ。
水族館の前には子供連れや恋人同士と思われる多くの人がいた。夏休みで、快晴の天気とあればこの人出も無理はないかもしれない。
そのとき、男の人の腕に抱きつくように絡んでいる女の子が目に映った。
ああいうことをする勇気は私にはないけど、すごく羨ましかった。
私がそういうことをしたら、どうするんだろう。
すごく冷めたことを言われそう。
宮野君は私の気持ちに気づいた様子はなく、あたりを見渡している。
「券を買ってくるから、待っていて」
私は彼の言葉に頷いていた。
わかっている。
だって、その程度の関係なんだから。
ここで手を引いて、どうしてそんなことを言うのって言えない関係。
だから私は自分の悲しい気持ちをこらえるために唇を軽く噛んだ。
水族館の前には子供連れや恋人同士と思われる多くの人がいた。夏休みで、快晴の天気とあればこの人出も無理はないかもしれない。
そのとき、男の人の腕に抱きつくように絡んでいる女の子が目に映った。
ああいうことをする勇気は私にはないけど、すごく羨ましかった。
私がそういうことをしたら、どうするんだろう。
すごく冷めたことを言われそう。
宮野君は私の気持ちに気づいた様子はなく、あたりを見渡している。
「券を買ってくるから、待っていて」
私は彼の言葉に頷いていた。