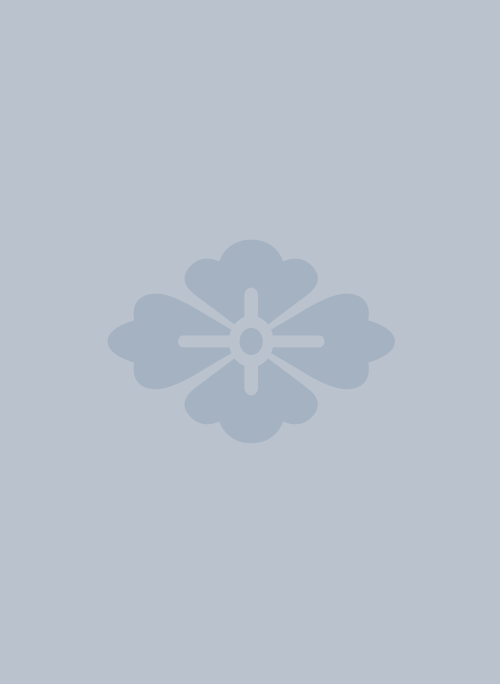葉月二日の朝、世都から再び書簡が届きました。
『本日、京、三条河原にて、秀次公の奥方様及び若様姫様、そしてその侍女を、処刑致す由。』
と、その書簡には書いてありました。
思わず書簡を手から落とし、はっと致しました。
早く、この書簡を燃やしてしまわねば。
ここしばらく、ずっと置いておいた火鉢を寄せ、中に書簡を入れて燃やし尽くしました。
そして、私は殿の許に急ぎました。
「殿、しばし、よろしゅうございましょうか。」
「何じゃ?」
「はい。
少しばかり、外出を致したく…」
「ならぬ。」
「え?」
殿は私を部屋の奥に入れ、向かい合って座るようになさいました。
「小松、そなた、知っておるな。」
「な、何の事にございましょうや。」
殿は声を押し殺し、
「亡き秀次公の事じゃ。」
と仰せられました。
「さ、さあ、何の事で…」
「しらばくれるでない。
才蔵からすべて聞いておる。
忍びの娘を飼っておると。」
「と、殿こそ何故ご存知なのです。
その件は未だ、公にはなっていませぬに。」
「……はあ。
我は真田家ぞ、忍びに詮索のひとつやふたつ、させておるに決まっておるであろう。」
「うっ…。」
「頼むから、大人しゅうしてくれ。」
「…い、嫌にございます!」
「何じゃと?」
「殿にご迷惑はかけませぬ!
何卒、私の知りたいという事を阻まないで下さいませ!」
「ならぬ。」
「殿!
…きゃっ。」
私は頭を深く下げましたが、殿は私の両肩を掴まれて無理矢理起こして参られました。
「どれだけ心配したと思うておる!
一歩間違わば、どうなるともしれぬのじゃぞ!!」
「わかっております…」
「いや、わかっておらぬ!
わしは、そなたが大切なのじゃ!
危ない目におうて欲しゅうない!
何故それをわかってくれぬ!!」
「と、殿…」
「…すまぬ。
しかし、わしは本心から申しておる。」
殿は私の肩から、そっと手を下ろされました。