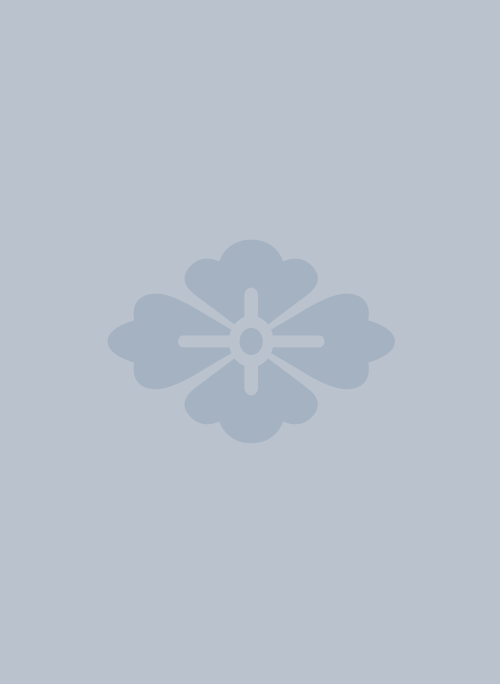夏に差し掛かり、蒸し暑い空気のせいか、今日は体が怠く感じます。
夏の衣服の腰巻姿で脇息にもたれていると、慌てた様子のふじが部屋に入って来ました。
額に滲んだ汗はこの暑さのためではないでしょう。
「ふじ、如何いたしたか。」
「は、はい…」
勢いよく入って来たわりに、歯切れの悪い返事をします。
「言うてみなければわからぬぞ。」
「それが……」
ふじはゆっくりと口を開きます。
私はふじの言葉を、すぐには理解出来ませんでした。
周りにいた侍女達も複雑そうな顔をしています。
ふじから聞いたそれは、私にとって驚き以外の何物でもありませんでした。