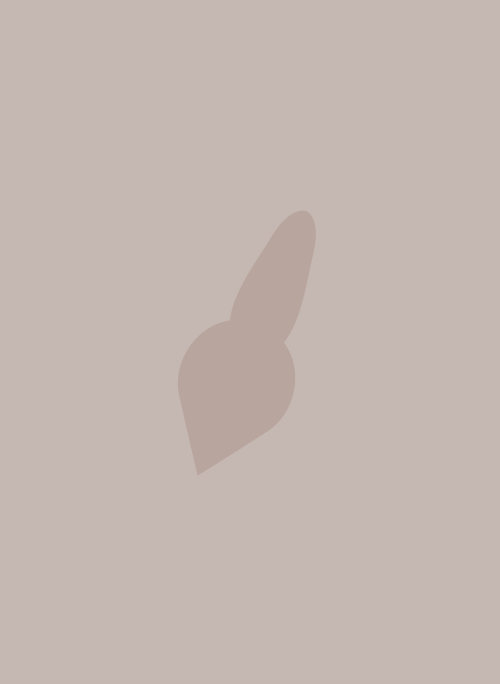上を向かされたあたしの額に、優しく、唇がおちる。
ちゅっ、と小さな音を立てて離れていくと、「ごめんな」って先生が呟いた。
「華南子の気持ち、理解っているつもりでいるけど……やっぱり、言葉にしてもらわないと駄目なときもあるんだよ」
「……恥ずかしい、って……言いました」
「それはそれ、これはこれ。本当に嫌なら、華南子は俺を殴ればいいよ」
「……それなら、あたしは先生を殴りまくることになりますけど……」
「え……っ、そんなに嫌だった?」
「冗談です」
笑いながら言ったあたしに先生も表情を崩して、それから唇が重なる。
「華南子、可愛い」
「先生……」