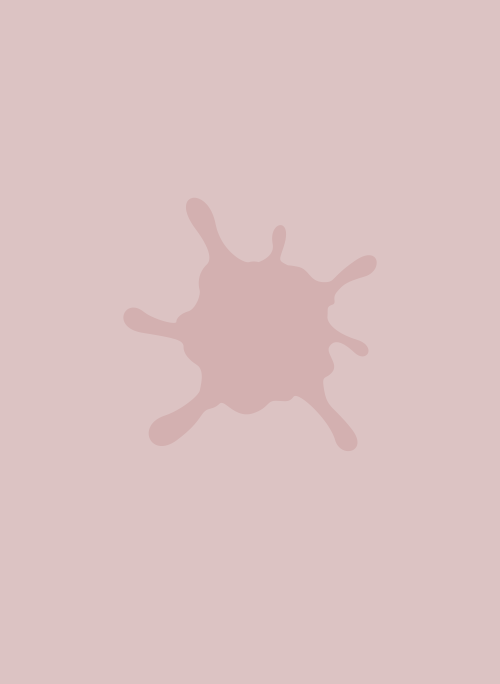剣山のように、隙間なく降って来た待ち針は彼の体を覆い、特に酷い顔はまるで一つのオブジェのように、傍から見れば恐ろしさを通り越して人とは見えないほど針が覆っていた。
口の中は頬を貫通した針が舌を縫いとめ、悲鳴さえも上げられない。
咽喉にびっしりと刺さった針は、気管に蓋をしたかのように、ただ、血液を溜め込んではそれを吐き出させようとする。
吐き出してはいけない。
思っても、身体の摂理など、止められるはずがない。
「ぅ、げ…え!」
咽喉を収縮させた瞬間に深々と刺さる針が蠢いて、舌が大きく動いた瞬間、舌に突き刺さっていた針もそれに合わせて舌の肉の中で動きだし、抉っては口内に鉄の味を広げる。
ボタボタ、と血液。
目を閉じても痛みは抜けない、正確には目が閉じられない。
男は恐る恐る、目元へと手を伸ばして異様に飛び出ているそれをゆっくりと抜き取る。
針。
視界は利かない。
真っ赤に塗りたぐられた部屋の中にいるようで、自分の眼球に針が刺さっていたというその事実にゾッとして、それでもまだ十数本刺さる眼球の針を取らなければという使命感に震える手が時折針を不用意に動かしながら抜き取ろうと、する。
異物が、普段は触れられることのないその柔らかいところに入り、摩擦しながら抜き取られるこの、寒気のする感覚。
眼球に刺さるその針を全て抜き取った時、男の身体には異様な疲労感と脂汗と血液が身体をずっしりと覆っていた。
止め処なく降って来る何百の針から逃れるようにして浴室を出ようとした瞬間。
ドアがキツク押さえられているかのように押してもビクとも動かなかった。まるで先ほどの窓のように。
体当たりをするように身体をぶつけ、何度もノブを動かして、ドアを叩いても、動く気配などなく、ミリ単位でさえも開く様子はなかった。