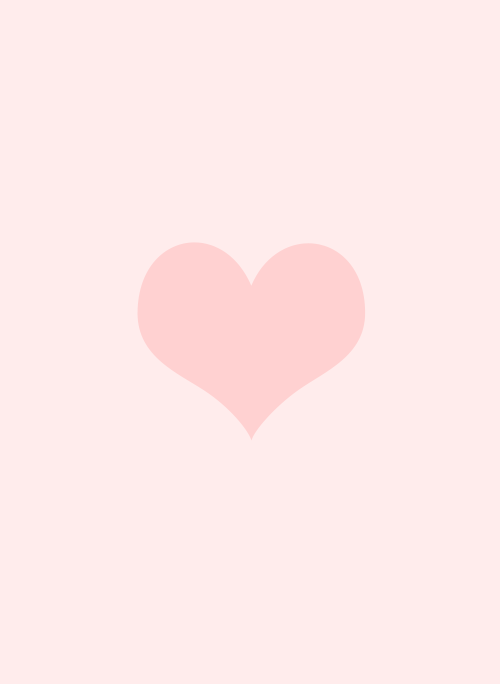ため息をつきながら何気なく外を眺めていると、見慣れた、いや見飽きた黒い車が校門前に停まった。
いらない、と言っても毎日迎えに来るものだから、最早いらないとさえ言うのがおっくうになってしまった。
運転席から降りてきた若年寄のような男、私のお付きに任命されてしまった嶌田(しまだ)が、これまた馬鹿丁寧に真っ直ぐ立って校門から出てくる生徒を眺めている。
普通、あのようなものが校門前に立っていたら不審者だろう。
けれどこの私立の学校は私の立場をどう思ってか、あれを黙認どころか歓迎すらしているのだ。
本当に、大人の世界って馬鹿らしい。
父から多額の寄付を受けているだけで、私に下手なことは言えない学校職員。
わざとテストを白紙で出そうが、注意すら出来ず、可笑しな言い訳を勝手に作っていた担任。
ううん、可笑しいのは大人だけじゃない。
クラスメートだって、その他の生徒だって、皆私を見る目はどこか違う。
「美人」
「スタイルがいい」
「勉強が出来る」
「何をしても様になる」
「品がある」
そんな台詞は、どこからでも聞こえてきた。
知っている、自分が羨望の眼差しで見られていることぐらい。
そしてそれが、自分の後ろにあるものに対しての畏怖だってことぐらい。
どれだけ、意味がないか、ってことぐらい。
だから、そんなことすら口にしないこの二人の方が、まだ良いと思っているのかもしれない。
いらない、と言っても毎日迎えに来るものだから、最早いらないとさえ言うのがおっくうになってしまった。
運転席から降りてきた若年寄のような男、私のお付きに任命されてしまった嶌田(しまだ)が、これまた馬鹿丁寧に真っ直ぐ立って校門から出てくる生徒を眺めている。
普通、あのようなものが校門前に立っていたら不審者だろう。
けれどこの私立の学校は私の立場をどう思ってか、あれを黙認どころか歓迎すらしているのだ。
本当に、大人の世界って馬鹿らしい。
父から多額の寄付を受けているだけで、私に下手なことは言えない学校職員。
わざとテストを白紙で出そうが、注意すら出来ず、可笑しな言い訳を勝手に作っていた担任。
ううん、可笑しいのは大人だけじゃない。
クラスメートだって、その他の生徒だって、皆私を見る目はどこか違う。
「美人」
「スタイルがいい」
「勉強が出来る」
「何をしても様になる」
「品がある」
そんな台詞は、どこからでも聞こえてきた。
知っている、自分が羨望の眼差しで見られていることぐらい。
そしてそれが、自分の後ろにあるものに対しての畏怖だってことぐらい。
どれだけ、意味がないか、ってことぐらい。
だから、そんなことすら口にしないこの二人の方が、まだ良いと思っているのかもしれない。
 | 野いちご](https://www.no-ichigo.jp/assets/1.0.825/img/logo.svg)