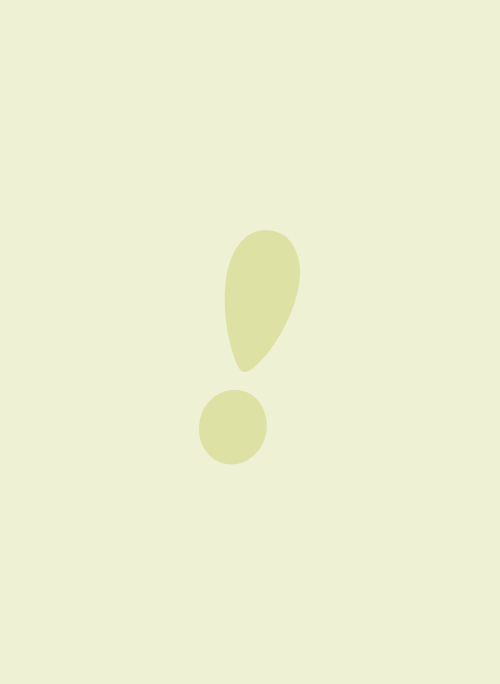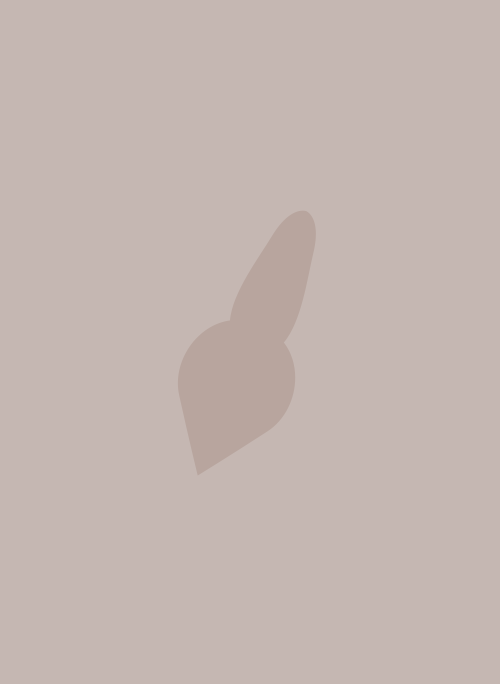長年生きてきて色々な事を学んだつもりだが、俺の中から出てきた、この不思議な感覚には悩まされる。
互いに距離を計るように、固まったまま。
暫くして、先に口を開いたのは彼女であった。
「本当にいたのね?」
「あぁ、いるよ。キミが結界を解き放つ前に現れちゃったけどね」
「それは、全然考えてなかったわね」
「すまない、キレイな首を傷つけてしまって」
彼女は黙ったまま横に首を振る。
「それは……運命(さだめ)だったのかもしれないわね」
運命? 否、今のは不可抗力だ。
「ねぇ、貴方はこの後私が解き放ったら、街の人たち皆に襲いにかかるのかしら?」
「まさか。そんな事しないし、仮にその道が出来たって俺たちは、そっちには行かないさ」
ハハハッ。俺たちはそんな恐ろしい種族に思われていたのか。
「本当?」
「この目を信じられない?」
真剣な眼差しで、キャサリンのブルーの瞳に、俺の正直な気持ちを送りつける。
「分かったわ。貴方なら信じられそうね」
「ありがとう」
人間にも、こんなに心の優しい人もいるのだな。
キャサリン、君が承諾をしてくれるのなら、俺は、今直ぐ連れて行きたい。結界を解き放つなんて、どうでもいい。
「ねぇウィルズリ、結界を解き放つの手伝ってくれる?」
想いも寄らない言葉が飛んできた。
俺たちを近づけない為の魔除けを、一緒に解き放つ?
彼女の思考についてゆけない。
「そうよ。私の大事な血を分けてあげたんだから、私の恋人になってよね」
「その意味を、理解していっているのか?」
彼女は、当たり前というように力強く微笑み返し、こうも言った。
「その結界は、愛する者が揃った時でないと、解けないっていうの」
この月夜の晩に、まだ見ぬ愛する者と出会える事だけを信じて、やって来たらしい。
無茶苦茶すぎる。仮に誰も現れなかった、らどうするつもりだったのか?
「現に出会ったじゃない。まさか、その当事者にいきなり会うとは思わなかったけどね」
それは俺も思わなかったよ。