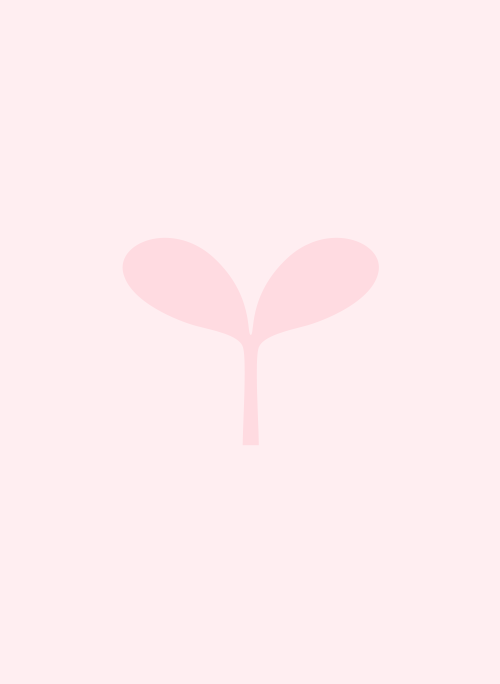「リヴィア…俺は妃はいらない。ただ、跡継ぎは残さなければならない。
だから…お前に側室になってもらいたいんだ」
それはつまり、愛してはいないが子供を作るための道具として側にいてほしい…、そういう事だった。
リヴィアは少しむっとした表情になり、再びヴェルヌに覆い被さった。
「リヴィア…」
「黙って…」
―――――
その時のリヴィアは、それほどヴェルヌに夢中になっていなかったため、少し考えさせてほしいと言っていた。
「あの時は正直…王族の子を生むなんて考えられなかった。でも…」
そう言うとリヴィアは机に腰掛け、ヴェルヌの頬にそっと手を当てお互いの唇がつくかつかないかの所まで近づけると色気のある声で言った。
「今は…あなたの子供が生みたい…」
そう言ってゆっくり目を閉じ唇を近づけた。
「やめろッ!」
リヴィアの体はヴェルヌによってはじかれ思わず体がよろめいた。
「ヴェルヌ、様…?」
ヴェルヌは椅子から立ち上がる事なく冷たい声でリヴィアに告げた。
「もうお前に用はない…もう二度とここへは来るな」