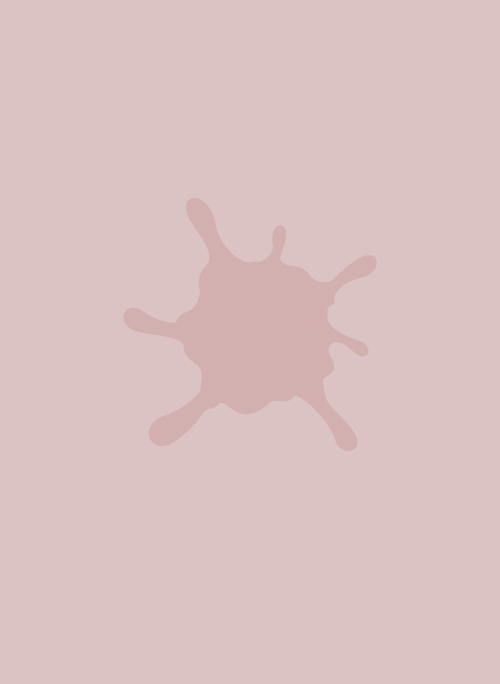「喉が渇いた。戻ろっか」
そう言った二人の目の前に立ちふさがった。
あたしがいることにそのとき気づいたのだろう。
彼女たちの表情が引きつっていた。
「勝手なこと言わないでよ。誰に言われたの? 誰から聞いたの?」
お母さんは本気で彼のことが好きだった。
あたしのことはいくら言われてもいい。
でも十八年、泣き言を言わずにあたしを育ててくれた母親に対してはそんなことを言われたくなかった。
母親が体を使ったとか、そんなことは彼女に対するこれ以上はない侮辱だった。
「何本気になっているのよ。冗談でしょう?」
田中文子は慌てた様子でつけくわえた。
でも彼女のそんな努力もむなしく、沢井ひろみは鼻で笑った。
そう言った二人の目の前に立ちふさがった。
あたしがいることにそのとき気づいたのだろう。
彼女たちの表情が引きつっていた。
「勝手なこと言わないでよ。誰に言われたの? 誰から聞いたの?」
お母さんは本気で彼のことが好きだった。
あたしのことはいくら言われてもいい。
でも十八年、泣き言を言わずにあたしを育ててくれた母親に対してはそんなことを言われたくなかった。
母親が体を使ったとか、そんなことは彼女に対するこれ以上はない侮辱だった。
「何本気になっているのよ。冗談でしょう?」
田中文子は慌てた様子でつけくわえた。
でも彼女のそんな努力もむなしく、沢井ひろみは鼻で笑った。