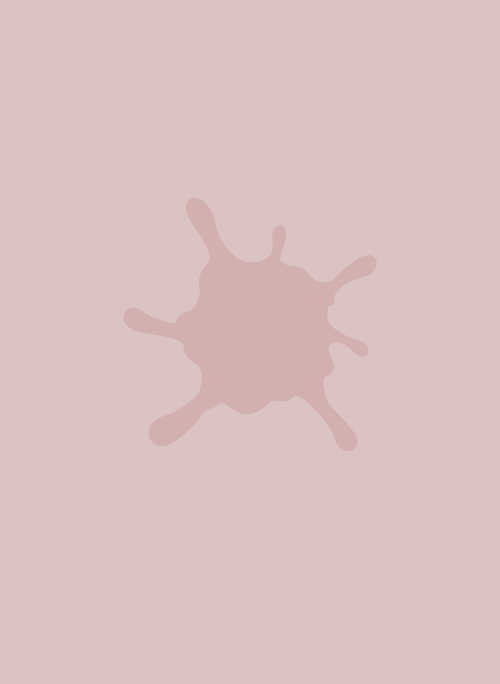彼女は吐き捨てるようにして言った。
あたしはそこまで聞いて、それが誰か分かった。
多分千春のことだ。
でも、もしあたしが彼の娘だということが知られたら、かなりややこしいことになるのかもしれない。
あたしはそのとき気づく。
彼は知らないけれど、そんないいわけが通用するとは思えなかった。
お母さんはそこまで考えてはいないだろうけど、彼女が嘘を吐いたのは正解だった。
「それなんだけどさ」
文子の声が一トーン低くなる。
「何?」
何か面白いおもちゃを見つけたような彼女の声が聞こえてきた。
「噂だけど、あの子の母親と監督ができているらしいよ。それでこの役をもらったって」
その言葉にあたしの心臓がどくんと鳴った。
あたしはそこまで聞いて、それが誰か分かった。
多分千春のことだ。
でも、もしあたしが彼の娘だということが知られたら、かなりややこしいことになるのかもしれない。
あたしはそのとき気づく。
彼は知らないけれど、そんないいわけが通用するとは思えなかった。
お母さんはそこまで考えてはいないだろうけど、彼女が嘘を吐いたのは正解だった。
「それなんだけどさ」
文子の声が一トーン低くなる。
「何?」
何か面白いおもちゃを見つけたような彼女の声が聞こえてきた。
「噂だけど、あの子の母親と監督ができているらしいよ。それでこの役をもらったって」
その言葉にあたしの心臓がどくんと鳴った。