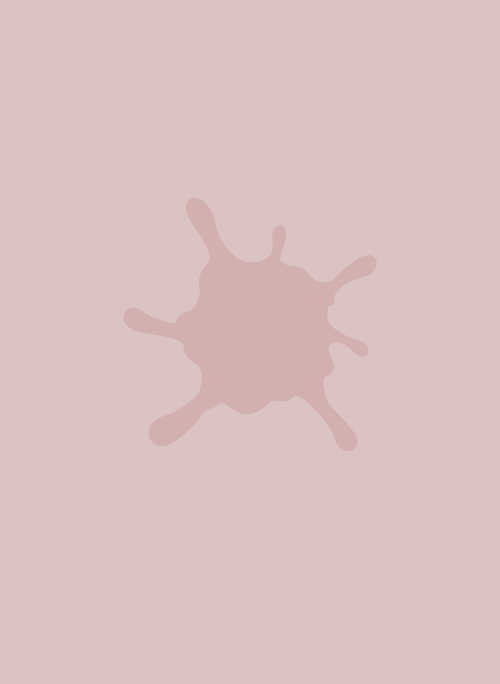春独特のぬくもりのある空気があたしの肌に触れる。
暑くも不快感もないこの空気はなんだか好きだった。
この時期は人が眠りを感じるということが分からなくもない。
「どこで会うの?」
「近くまで来てくれているはず」
千春の後をついていく。
彼女の足が少し古ぼけた飲食店の前で止った。
そこには特製オムライスという看板がかけられていた。
ここのオムライスはそんなにおいしいのだろうか。
あたしは看板を見ながらそんなことを考える。
あたしたちが店の中に入ると、鈴の音が店内に響き渡る。
千春は店の店主らしき若い女性に手を振ると、奥に入っていく。
店の中は明かりの量を徹底的に落としているのだろう。
窓から差し込む太陽の光が店内を照らし出していた。
その光がちょっと幻想的に見えた。
暑くも不快感もないこの空気はなんだか好きだった。
この時期は人が眠りを感じるということが分からなくもない。
「どこで会うの?」
「近くまで来てくれているはず」
千春の後をついていく。
彼女の足が少し古ぼけた飲食店の前で止った。
そこには特製オムライスという看板がかけられていた。
ここのオムライスはそんなにおいしいのだろうか。
あたしは看板を見ながらそんなことを考える。
あたしたちが店の中に入ると、鈴の音が店内に響き渡る。
千春は店の店主らしき若い女性に手を振ると、奥に入っていく。
店の中は明かりの量を徹底的に落としているのだろう。
窓から差し込む太陽の光が店内を照らし出していた。
その光がちょっと幻想的に見えた。