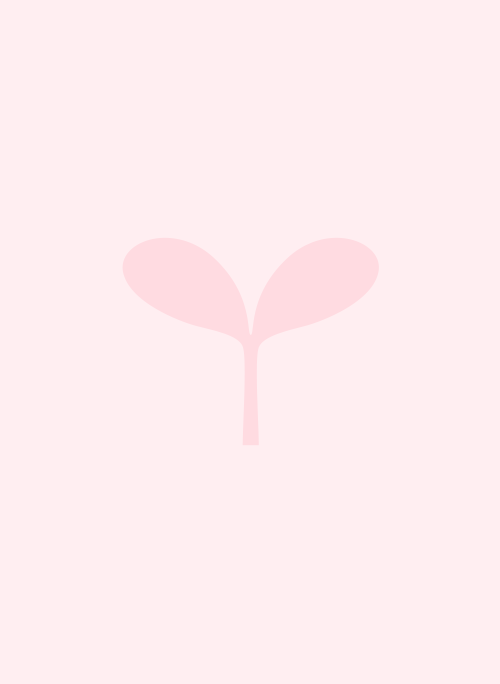鳥英の笑顔が瞼の裏をちらついて、俺は両手を握りしめる。
彼女もまた、何も知らないのだ。
当然だ。
あの夜のことは、この世で親父殿と伊羽青文、俺と留玖とりつ殿しか知らない。
俺たちが、自分の家を陥れた張本人だと、何も知らずに
彼女は快く俺に力を貸してくれて──そして──
「クソッ!」
俺は拳で小さく膝を叩いた。
「頼みもしねえのに、面倒なこと調べてきやがるぜ」
「知らせないほうが良かったか?」
「いや」
俺は宗助に笑いかけた。
自分でも弱々しい笑みになっているのではないかという気がする笑い方になった。
「よく知らせてくれた。礼を言う」
知らなければ良かったと思うが、
知らなければ許されないことだったと思う。
彼女もまた、何も知らないのだ。
当然だ。
あの夜のことは、この世で親父殿と伊羽青文、俺と留玖とりつ殿しか知らない。
俺たちが、自分の家を陥れた張本人だと、何も知らずに
彼女は快く俺に力を貸してくれて──そして──
「クソッ!」
俺は拳で小さく膝を叩いた。
「頼みもしねえのに、面倒なこと調べてきやがるぜ」
「知らせないほうが良かったか?」
「いや」
俺は宗助に笑いかけた。
自分でも弱々しい笑みになっているのではないかという気がする笑い方になった。
「よく知らせてくれた。礼を言う」
知らなければ良かったと思うが、
知らなければ許されないことだったと思う。