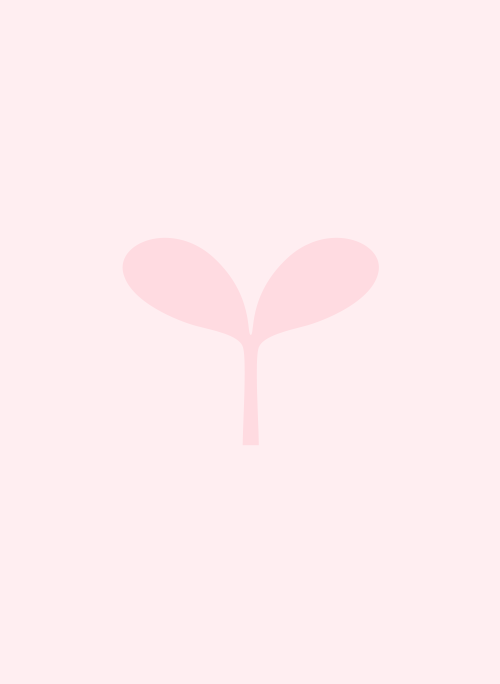神崎は慌てた。
弁明を聞くと──
奉行所で浮いた存在の町方与力は、積もりに積もった日々のうっぷんを、ずっとこのようにして毎夜毎夜樹木をぶっ叩くことで晴らしていたらしい。
奉行所での神崎の様子を思い出すと、その気持ちはわからなくもない気もしたが……
「その頭の蝋燭は何だ」
俺はどこからどう見ても丑の刻参りの呪い装束といった風体の神崎に尋ねた。
「これは、その……夜は暗いのでな……両手で木刀を振るいやすくための工夫だ……」
己の憂さ晴らしがご近所中の噂──どころか城下の怪談になっていたとは、露ほども思わなかったらしく、神崎は意気消沈した様子で答えた。
「そんな、髪まで下ろして寝間着姿でよ」
あきれる俺に、
「それは──さすがに、誰かに見られてすぐに武士とわかってはまずかろうと……」
神崎はモゴモゴと説明した。
一応、他人様の目に触れては問題だという意識と、武士としてあるまじき行いだという自覚はあったらしい。
「そっちのほうが目立つだろうが」
俺は頭を押さえた。
「だからいつも、このように人気のない刻限を選んでいたんだ」
かくして丑の刻参りの鬼女の怪談の出来上がりというわけか。
今は、神社から場所を移して
城下の夜道を三人で武家屋敷の界隈へと引き返しているところだが、
確かに草木も眠る丑三つ時。
こんな格好の神崎と一緒でも、周囲を歩く人影は俺たち以外にはなく、視線を向けてくる者もいない。
弁明を聞くと──
奉行所で浮いた存在の町方与力は、積もりに積もった日々のうっぷんを、ずっとこのようにして毎夜毎夜樹木をぶっ叩くことで晴らしていたらしい。
奉行所での神崎の様子を思い出すと、その気持ちはわからなくもない気もしたが……
「その頭の蝋燭は何だ」
俺はどこからどう見ても丑の刻参りの呪い装束といった風体の神崎に尋ねた。
「これは、その……夜は暗いのでな……両手で木刀を振るいやすくための工夫だ……」
己の憂さ晴らしがご近所中の噂──どころか城下の怪談になっていたとは、露ほども思わなかったらしく、神崎は意気消沈した様子で答えた。
「そんな、髪まで下ろして寝間着姿でよ」
あきれる俺に、
「それは──さすがに、誰かに見られてすぐに武士とわかってはまずかろうと……」
神崎はモゴモゴと説明した。
一応、他人様の目に触れては問題だという意識と、武士としてあるまじき行いだという自覚はあったらしい。
「そっちのほうが目立つだろうが」
俺は頭を押さえた。
「だからいつも、このように人気のない刻限を選んでいたんだ」
かくして丑の刻参りの鬼女の怪談の出来上がりというわけか。
今は、神社から場所を移して
城下の夜道を三人で武家屋敷の界隈へと引き返しているところだが、
確かに草木も眠る丑三つ時。
こんな格好の神崎と一緒でも、周囲を歩く人影は俺たち以外にはなく、視線を向けてくる者もいない。