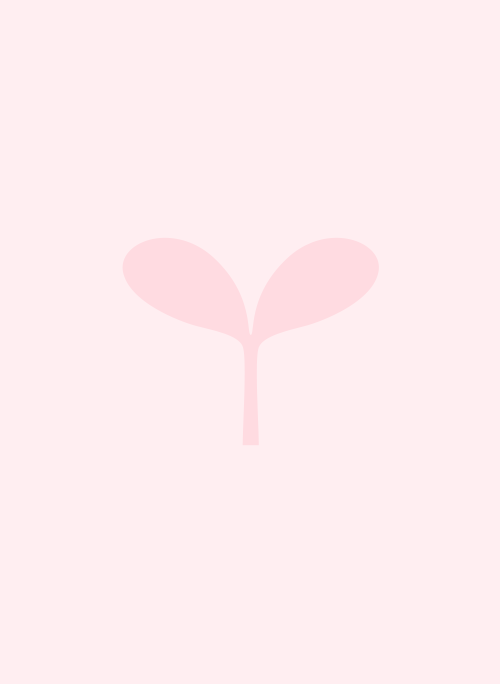【円】
社殿の裏に回って、雑木林の奥へと歩を進めると、
「──ええい、呪ってやる……あの分からず屋め、死ね! 死ねえ!」
風に乗ってそんな声が届き、俺は眉間に皺を寄せた。
コーン、コーンという、何かを叩くような音と共に、
「権力に平伏してすぐにヘコヘコしおって! 町方としての誇りはないのか、あの町奉行めが!」
聞こえてくる声には、耳に覚えがあった。
「ええい、忌々しい高津図書め! 殺してやる! 死ね! 死ね!」
んん?
「だいったい、あのボンボンめ! 我が物顔で捜査に手出ししてきおって! 結城円士郎め! あやつも死ね! 死んでしまえ!」
……おいコラ。
「キェエエエッ! それもこれも本を正せば、あやつをこの俺の仕事に介入させてきおった城代家老の伊羽青文のせいだ! 呪われろ! 青二才の家老めが! 死ねーッ!」
火を灯した二本の蝋燭を鉢巻きで頭にくくりつけ、
白い寝間着姿で呪いの言葉をわめき散らしながら、
境内の樹木に向かって、手にした木刀を滅多打ちに打ちつけているのは──
見知った顔の『男』だった。
「いやあああ──っ」
俺の横で、その場に座り込んだ留玖が悲鳴を上げ、
「誰だァ──」
ゼハァー、ゼハァー、と肩で息を切らしながら、憤怒の形相で男がこちらを向き、
「やだあああああ──!?」
のしのしと歩み寄ってきた男に向かって、錯乱した留玖が刀を抜き放った。
「ぬお!? 貴様らは──」
近くまでやってきて、蝋燭の明かりが照らす俺たちの顔に気づいたのか、
俺と留玖を前にして立ち尽くしたその『鬼女』に、
俺は思いきり冷ややかな視線を浴びせた。
「神崎帯刀、何やってんだアンタ?」