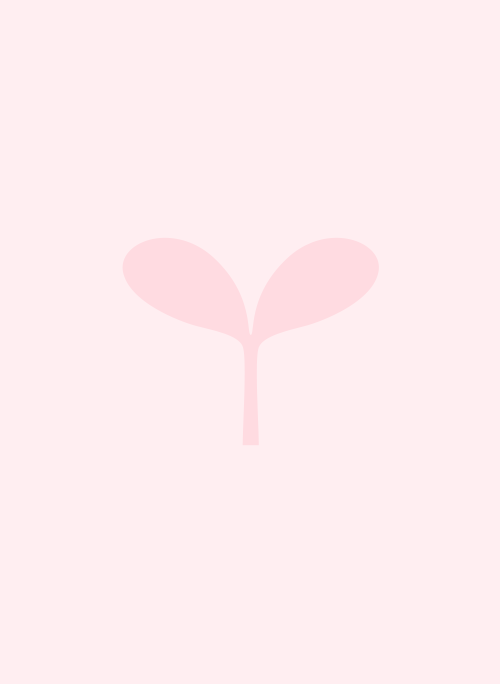【剣】
円士郎はあきれ返っている様子だった。
あきれられても仕方がない。
十七にもなって、一人で寝るのが怖くて、こんなはしたない真似をするなんて、
自分でもどうかしていると思う。
武家の娘としてあるまじき行為だ。
面目無さと恥ずかしさで顔を上げられなかった。
「仕方ねえ」と、意を決した声がして、恐る恐る円士郎を見ると、
「今回だけだぞ」
障子から月の光が差し込む薄暗がりで、
円士郎は何かが吹っ切れたような表情をしていて、
その顔がにやっとした。
「じゃないと、俺も何するかわからねーからな」
「え……」
私がぎくりとなるような、艶っぽさのある声音だった。
それから円士郎は私の刀も一緒に枕元に置いて、
突っ立っている私の後ろで襖を閉めた。
布団に入って場所を空けてくれて、
ほら、と促されて、
ホッとした途端──
急に、恐怖とは別の緊張感が走って、胸がどきどきし始めてしまった。
「何やってんだ、入れよ」
「うん……」
私は円士郎からできるだけ離れた
布団の端っこに潜り込んだ。