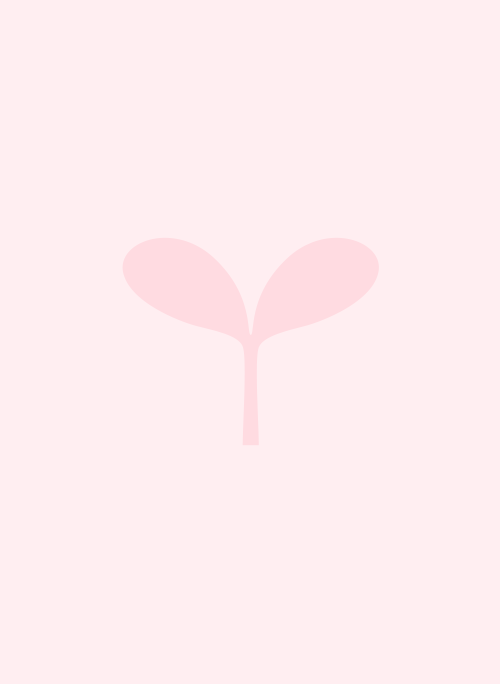え──?
家族に捨てられた時のような感覚が、再び背中を這い上った。
「留玖は……お前の妹ではないか……!」
父上の声が聞こえて、
「私は、もう留玖を自分の妹だとは思うことができません!」
円士郎はそう言った。
エン……?
なんで……?
昨日の夜の、私に突き飛ばされた円士郎の顔が脳裏に浮かんだ。
私はがくがくと手足が震えて、その場に座り込んだ。
結城家から追い出したいと思うほど、私は円士郎に嫌われたの──!?
妹でいるだけで幸せだと思い込もうとした。
けれど
円士郎の妹であることすら、許されないというのだろうか。
私は、ここに……
父上や母上のいる、この結城家にもう置いてもらえないの……エン?
「留玖からも話を聞く。お前は部屋に戻って少し頭を冷やしておれ」
父上がそう言って、襖が開いて円士郎が出てきた。
私はとっさに、隣の部屋に隠れて円士郎をやり過ごした。
部屋の境にある襖の向こう側からは、父上と母上が何か話している声がボソボソと聞こえている。
怖々、襖に近づいて話の内容を聞こうとしたら……
「留玖が女だということが初めからわかっていたら、他に手もあったのだがな……」
溜息混じりに父上がそうこぼし、
「留玖を養女にしたのは、儂の間違いだったか──」
目の前が真っ暗になるような言葉が耳に飛び込んできて、
ガタン、と──
よろめいて襖に手を突き、私は大きな音を立ててしまった。
家族に捨てられた時のような感覚が、再び背中を這い上った。
「留玖は……お前の妹ではないか……!」
父上の声が聞こえて、
「私は、もう留玖を自分の妹だとは思うことができません!」
円士郎はそう言った。
エン……?
なんで……?
昨日の夜の、私に突き飛ばされた円士郎の顔が脳裏に浮かんだ。
私はがくがくと手足が震えて、その場に座り込んだ。
結城家から追い出したいと思うほど、私は円士郎に嫌われたの──!?
妹でいるだけで幸せだと思い込もうとした。
けれど
円士郎の妹であることすら、許されないというのだろうか。
私は、ここに……
父上や母上のいる、この結城家にもう置いてもらえないの……エン?
「留玖からも話を聞く。お前は部屋に戻って少し頭を冷やしておれ」
父上がそう言って、襖が開いて円士郎が出てきた。
私はとっさに、隣の部屋に隠れて円士郎をやり過ごした。
部屋の境にある襖の向こう側からは、父上と母上が何か話している声がボソボソと聞こえている。
怖々、襖に近づいて話の内容を聞こうとしたら……
「留玖が女だということが初めからわかっていたら、他に手もあったのだがな……」
溜息混じりに父上がそうこぼし、
「留玖を養女にしたのは、儂の間違いだったか──」
目の前が真っ暗になるような言葉が耳に飛び込んできて、
ガタン、と──
よろめいて襖に手を突き、私は大きな音を立ててしまった。