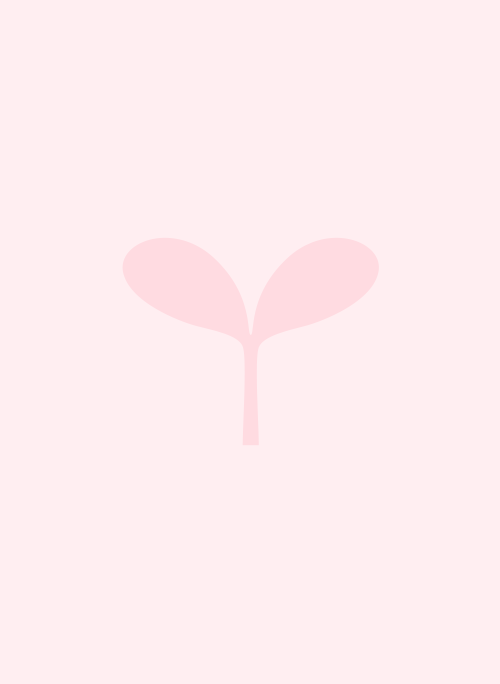彼が何に対して謝っているのか、
どうして謝るのか、
私にはわからなくて、戸惑ったけれど、
「ごめんな、留玖」
円士郎は繰り返して、左手で私の頭をなでて──
「ごめん……俺は──」
その声が今にも消えてしまいそうで、
いつもの円士郎からは想像もできない程、
あまりにも弱々しくて
私はそろそろと円士郎の背に手を回して、ゆっくりその背中をなでた。
「なあに? エン、どうしたの……?」
血の臭いがして、
円士郎の匂いがして、
彼の温もりが伝わってきて、
彼が生きていることを再確認する。
円士郎の声を聞いた時のように、私は全身の力が抜けていくような安心感に包まれて──
「都築様は死んだか」
間近から聞こえた低い声に、再び全身を緊張が駆け抜けた。
どうして謝るのか、
私にはわからなくて、戸惑ったけれど、
「ごめんな、留玖」
円士郎は繰り返して、左手で私の頭をなでて──
「ごめん……俺は──」
その声が今にも消えてしまいそうで、
いつもの円士郎からは想像もできない程、
あまりにも弱々しくて
私はそろそろと円士郎の背に手を回して、ゆっくりその背中をなでた。
「なあに? エン、どうしたの……?」
血の臭いがして、
円士郎の匂いがして、
彼の温もりが伝わってきて、
彼が生きていることを再確認する。
円士郎の声を聞いた時のように、私は全身の力が抜けていくような安心感に包まれて──
「都築様は死んだか」
間近から聞こえた低い声に、再び全身を緊張が駆け抜けた。