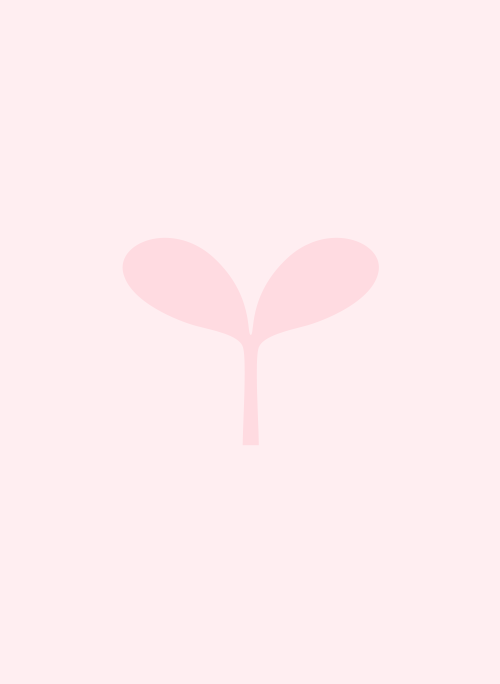「えっ……」
私はびっくりして、彼の腕の中でもがいて、円士郎の顔を見ようとした。
ふふっと笑う気配がして、円士郎が腕を解いてくれて、
見上げた私の視線とぶつかった彼の瞳は、とても優しい色をしていた。
彼が死を覚悟していた時と同じ、揺るぎない目だった。
「そ、そんなの……ダメだよ……」
私は、困ってしまって
うつむいて
「いつも、エンはそうやって、私を困らせることばかり言うんだから……」
ボロボロになっている円士郎の着物に向かって呟いて、
円士郎の体から笑う振動が伝わってきた。
私はびっくりして、彼の腕の中でもがいて、円士郎の顔を見ようとした。
ふふっと笑う気配がして、円士郎が腕を解いてくれて、
見上げた私の視線とぶつかった彼の瞳は、とても優しい色をしていた。
彼が死を覚悟していた時と同じ、揺るぎない目だった。
「そ、そんなの……ダメだよ……」
私は、困ってしまって
うつむいて
「いつも、エンはそうやって、私を困らせることばかり言うんだから……」
ボロボロになっている円士郎の着物に向かって呟いて、
円士郎の体から笑う振動が伝わってきた。