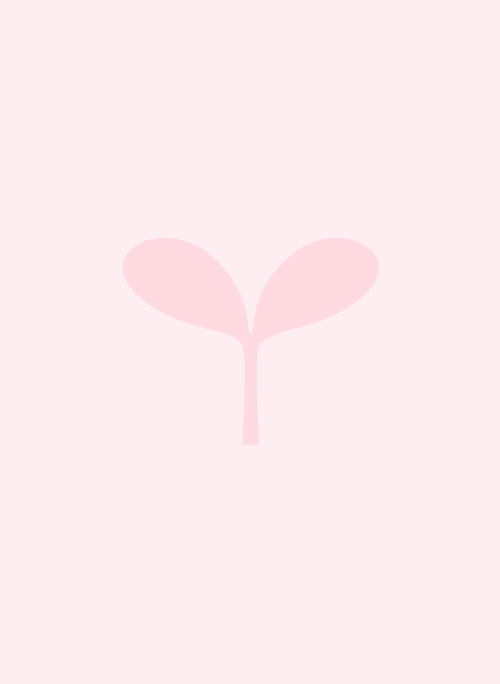青文が慌てて身をひねり、
彼の頬をかすめて通り過ぎた「それ」は、背後にあった石の灯篭を撃ち抜いた。
「鎖分銅か……」
青文が、石に穴を空けた物体の正体を口にして、
兵衛が鎖を引き、両端に鎌と分銅のついた武器を再びたぐり寄せ、
鎖の部分を握って、ひゅるひゅると回転させ始めた。
私は、父上から聞いたこの武器のやっかいな特性を思い出す。
鋭い刃をそなえた鎌だけじゃない。
反対側の端についた分銅も十分致命傷を与える威力を宿しているし、鎖そのものも巻きつけたりすることで武器になる。
「仕える国を失って、俺の父親と母親は自刃して死んで、俺は父親と縁のあった鎖鎌の道場主のもとに預けられた」
鎖鎌を回転させながら、兵衛はそう語って、
「貴様が、この件で闇鴉の夜叉之助に手を貸したのは──この国も己の国と同じように滅ぼしてやろうという考えからか」
青文が槍をかまえ直して、尋ねた。
「まさか」と、上流階級の士分の出である男は笑って、
「俺が武家の人間だったのは、はるか昔の話だぜ?
断蔵じゃあるまいし、今さら国なんざどうでもいいね。
俺が話に乗ったのは、先代の頭の頃からのつき合いがあった行逢神の平八の野郎の誘いがあったのと──お前の姿をこの町で目撃した者がいると聞いたからだ」
殺し屋は、金髪緑眼の青年をにらんだ。
「鎖鎌の修行を積んだ俺は、成長して腕を生かして殺しの稼業を始めて──仕事が軌道に乗ってきた矢先に、ガキのお前さんにハメられて島送りだ。
さァて、この入れ墨の恨み、晴らさせてもらおうか!」
兵衛が鎖鎌を放つ。
青文は、今度は槍を使わずにそれをよけて──
彼の頬をかすめて通り過ぎた「それ」は、背後にあった石の灯篭を撃ち抜いた。
「鎖分銅か……」
青文が、石に穴を空けた物体の正体を口にして、
兵衛が鎖を引き、両端に鎌と分銅のついた武器を再びたぐり寄せ、
鎖の部分を握って、ひゅるひゅると回転させ始めた。
私は、父上から聞いたこの武器のやっかいな特性を思い出す。
鋭い刃をそなえた鎌だけじゃない。
反対側の端についた分銅も十分致命傷を与える威力を宿しているし、鎖そのものも巻きつけたりすることで武器になる。
「仕える国を失って、俺の父親と母親は自刃して死んで、俺は父親と縁のあった鎖鎌の道場主のもとに預けられた」
鎖鎌を回転させながら、兵衛はそう語って、
「貴様が、この件で闇鴉の夜叉之助に手を貸したのは──この国も己の国と同じように滅ぼしてやろうという考えからか」
青文が槍をかまえ直して、尋ねた。
「まさか」と、上流階級の士分の出である男は笑って、
「俺が武家の人間だったのは、はるか昔の話だぜ?
断蔵じゃあるまいし、今さら国なんざどうでもいいね。
俺が話に乗ったのは、先代の頭の頃からのつき合いがあった行逢神の平八の野郎の誘いがあったのと──お前の姿をこの町で目撃した者がいると聞いたからだ」
殺し屋は、金髪緑眼の青年をにらんだ。
「鎖鎌の修行を積んだ俺は、成長して腕を生かして殺しの稼業を始めて──仕事が軌道に乗ってきた矢先に、ガキのお前さんにハメられて島送りだ。
さァて、この入れ墨の恨み、晴らさせてもらおうか!」
兵衛が鎖鎌を放つ。
青文は、今度は槍を使わずにそれをよけて──